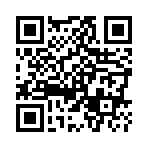2017年02月05日
勝連城址の謎/ローマ帝国コインの発見5
さてと解体屋のおじさんです、こんばんは。
夜半に目が覚めましたので、趣味の日曜日の歴史ブログを書こうと思いますが。
そして本日は、前回がマラッカ海峡のマラッカ王国の話で、琉球王国との貿易を行っていたことを突き止めましたので、話をさかのぼりローマ帝国コイン発行の時代へと遡ります。
起承転結の、「転」のところですね・・・実は「結」はまだ考えてない(汗)ま、でも、書いていたら何かしら考えが浮かぶでしょうから、とりあえず書き進みたいと思います。
さて、まずはこちらのURLをご覧ください。
http://www.augustus.to/coin/ZN_j_constantinus.html
勝連城址で発見されたローマ帝国コインは3世紀から4世紀のもの、ということで恐らくはコンスタンティヌス帝かヨウィアヌス帝のコインと見受けられます。
コンスタンティヌス帝は東西に分かれ分裂していた帝国の統一に成功、「大帝」とも尊称されます。この方は禁教とされていたキリスト教を公認し、宗教の自由を与えた人物でもあります。ミラノ勅令と言います。偉大ですね。
ただ、キリスト教がローマ帝国の国教とされるのは、さらに先でテオドシウス一世の時になります。
なので肖像画がコインに描かれているわけですが・・・あと、もう一人の方も書くか。次はヨウィアヌス帝を。
ちょいと資料を調べましたが・・・先帝が副帝も指名してなかったので軍隊によって選出されたとしか書かれてないですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%8C%E3%82%B9
ふむ・・・・ちょいと行き詰ったので話を変えまして、次は貨幣の歴史の話を。引用します。
「地域の覇者となったローマ帝国は紀元前269年頃より自国通貨の大量生産を始める。」
「ユノ・モネタ神殿に隣接した造幣局より鋳造され、そこからmoneyとmintという言葉が生まれたと思われる」
引用元 貨幣の「新」世界史 ハンムラビ法典からビットコインまで
んー・・・ローマ帝国はあまり勉強してないからなあ・・・琉球王国とのつながりも薄すぎて、ぴんと来ない。
ま、ただ、三世紀に鋳造され、勝連に到達する14世紀から15世紀までの間に、ユーラシア大陸を漂流していたのでしょう。壮大な話だ(^^;;
そして、マラッカ海峡のマラッカ王国にいつかはたどり着き、交易をつかさどる四人の貿易長官のうち、東アジア担当(中国、琉球王国、チャンパ王国担当)から琉球王国へと向かい出荷されたと。
書いているうちにだんだん、頭がさえてきました。
多分、本当にラストは次回かその次くらいのブログになるかと思います。
ラストは勝連城址の最大の名君、麒麟児「阿麻和利」とローマ帝国コインの話を書くことになるかと。
では、朝のコーヒータイム、お先に失礼します。
( ^^) _U~~
夜半に目が覚めましたので、趣味の日曜日の歴史ブログを書こうと思いますが。
そして本日は、前回がマラッカ海峡のマラッカ王国の話で、琉球王国との貿易を行っていたことを突き止めましたので、話をさかのぼりローマ帝国コイン発行の時代へと遡ります。
起承転結の、「転」のところですね・・・実は「結」はまだ考えてない(汗)ま、でも、書いていたら何かしら考えが浮かぶでしょうから、とりあえず書き進みたいと思います。
さて、まずはこちらのURLをご覧ください。
http://www.augustus.to/coin/ZN_j_constantinus.html
勝連城址で発見されたローマ帝国コインは3世紀から4世紀のもの、ということで恐らくはコンスタンティヌス帝かヨウィアヌス帝のコインと見受けられます。
コンスタンティヌス帝は東西に分かれ分裂していた帝国の統一に成功、「大帝」とも尊称されます。この方は禁教とされていたキリスト教を公認し、宗教の自由を与えた人物でもあります。ミラノ勅令と言います。偉大ですね。
ただ、キリスト教がローマ帝国の国教とされるのは、さらに先でテオドシウス一世の時になります。
なので肖像画がコインに描かれているわけですが・・・あと、もう一人の方も書くか。次はヨウィアヌス帝を。
ちょいと資料を調べましたが・・・先帝が副帝も指名してなかったので軍隊によって選出されたとしか書かれてないですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%8C%E3%82%B9
ふむ・・・・ちょいと行き詰ったので話を変えまして、次は貨幣の歴史の話を。引用します。
「地域の覇者となったローマ帝国は紀元前269年頃より自国通貨の大量生産を始める。」
「ユノ・モネタ神殿に隣接した造幣局より鋳造され、そこからmoneyとmintという言葉が生まれたと思われる」
引用元 貨幣の「新」世界史 ハンムラビ法典からビットコインまで
んー・・・ローマ帝国はあまり勉強してないからなあ・・・琉球王国とのつながりも薄すぎて、ぴんと来ない。
ま、ただ、三世紀に鋳造され、勝連に到達する14世紀から15世紀までの間に、ユーラシア大陸を漂流していたのでしょう。壮大な話だ(^^;;
そして、マラッカ海峡のマラッカ王国にいつかはたどり着き、交易をつかさどる四人の貿易長官のうち、東アジア担当(中国、琉球王国、チャンパ王国担当)から琉球王国へと向かい出荷されたと。
書いているうちにだんだん、頭がさえてきました。
多分、本当にラストは次回かその次くらいのブログになるかと思います。
ラストは勝連城址の最大の名君、麒麟児「阿麻和利」とローマ帝国コインの話を書くことになるかと。
では、朝のコーヒータイム、お先に失礼します。
( ^^) _U~~
Posted by white_yamada at
05:02
│Comments(0)
2017年01月15日
勝連城址の謎/ローマ帝国コインの発見4
さてと解体屋のおじさんです、こんばんは。
今日も勝連城址のローマ帝国コインの話になりますが・・・
おさらいとして話を元に戻しますが、勝連が滅んだのは1458年で、それ以降は貿易は行われていない、なので1458年以前の貿易の物流を辿っていくと、ローマ帝国コインが何処から流れてきたのか推測しやすい、
あとは近代以前なのでユンボウもダンプもクレーンも無く、港町は全部手作りになるので、そんなに簡単に町を一つ作れない、町が有るという事は人や食べ物の物流が有るという事でもあるので、1458年近くの船の寄港地がわかれば、そこに町が有り食料や娯楽(酒場や売春所)が有るのでローマ帝国コインも確保しやすい、
自分はその目安として、中国の鄭和の寄港地を目安にしました。これなら1406年の航海なので、勝連の繁栄の時期と重なるところが大きい。ただ、自分が知らないというだけで、他の国の航海地図は有るかもです。ご存知の方は教えてくださいませ。<(_ _)>
そして、前回に各寄港地をまわっていきまして、ようやくマラッカ海峡までたどりつきました。そこを掘り下げます。
マラッカ海峡なんですが、中国の唐が全盛期の時は、それほど栄えておりません。まあ、当然です。唐みたいな巨大国家が有り、治安もよくて通行税もないのなら、あえて危険な海のルートをたどる必要性は、あまりない・・・
あ、念のために書いておきます。必要性がないとはいっても、それでも海のルートは重要でして、それは何故かと言いますと、大量の貨物を運ぶ方法は前近代では船しかないのです。陸上の貨物輸送だと馬車しかないので、それだと船の積載量には負けてしまいます。
なので、必要性はあまりないとはいっても、それなりには繁栄していましたが、超大国「唐」の崩壊で海上輸送ルートはにわかに脚光を浴びます。陸上で小さな国家が乱立すると、通行税は取られるし、治安だって悪いし、なので良いことがあまりないのです。前近代の海は、領海という概念が薄いので、船さえ持ってたら好き勝手にどこまでも行けますし。
んー・・・多分ですが、船は中国の帆船でしょう。というのも、まだ西欧は十字軍で大騒ぎで海洋進出の準備がされてない。
どういう船かというと、wikiから参照。
「中国の帆船(8~18世紀)[編集]
北宋時代に高麗へ派遣する使節用として造られた帆船は全長約110メートル積載量1100トン以上で、見た事のない大船だと記される。一般の貿易船としては、積載量275トン程度の大船から万斛船と呼ばれる600~900トン程度の巨大帆船まで様々な種類の船が用いられた。戦闘船は速度が重視され、一日千里を航行すると記録されている。
ヴェネツィアの旅行家マルコ・ポーロ(Marco Polo,1254年 -1324年)は20年近く元朝のクビライ・ハーンに仕えた。そのときのことを口述した『東方見聞録』において、元朝の南方交易用の帆船は、4本のマストを持ち乗員は60名程度であること、竜骨(キール)によって船体は高い強度を保っていること、浸水しても沈没を免れる隔壁構造の船体を採用していること、羅針盤によって正確な遠洋航行が可能であることを報告している。
中国の明朝では鄭和が1405年から1433年にかけて7回の大航海を行った。航海した範囲は東南アジア、インド、アラビア半島、アフリカ東岸にまでわたった。これらの航海には長さ173m、幅56mにも及ぶ巨大な帆船が用いられた(詳細は項目「鄭和」を参照のこと)。」
そして、その時期にマラッカ海峡を治めていたのはマラッカ王国。マラッカ海峡はムラカとも言うそうです。ムラカ港務長官は四人いて、一人が中国などの東アジア担当、細かく言いますと、中国、琉球王国、チャンパ―を担当しておりました。
ほら、勝連貿易にたどり着いた(--d
マラッカ海峡を経由して勝連へと貿易していた可能性が高いです。そして、その中にローマ帝国コインも入っていた、と。
ちなみに後の話になりますが、マラッカ海峡は勝連が滅んだ1458年のあとの1511年にポルトガルが攻めてきて占拠され、ポルトガル海上帝国の主要拠点の一つにされます。でも、その前はマラッカ王国は繁栄していたと。
んー・・・そうだな、そうするか。
もう、ここまで書いてしまったので、開き直ってローマ帝国コイン発行の時代まで遡る事にします。
とんでもなく長いブログになってしまったな(笑)
今日はここまでにします。
朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
今日も勝連城址のローマ帝国コインの話になりますが・・・
おさらいとして話を元に戻しますが、勝連が滅んだのは1458年で、それ以降は貿易は行われていない、なので1458年以前の貿易の物流を辿っていくと、ローマ帝国コインが何処から流れてきたのか推測しやすい、
あとは近代以前なのでユンボウもダンプもクレーンも無く、港町は全部手作りになるので、そんなに簡単に町を一つ作れない、町が有るという事は人や食べ物の物流が有るという事でもあるので、1458年近くの船の寄港地がわかれば、そこに町が有り食料や娯楽(酒場や売春所)が有るのでローマ帝国コインも確保しやすい、
自分はその目安として、中国の鄭和の寄港地を目安にしました。これなら1406年の航海なので、勝連の繁栄の時期と重なるところが大きい。ただ、自分が知らないというだけで、他の国の航海地図は有るかもです。ご存知の方は教えてくださいませ。<(_ _)>
そして、前回に各寄港地をまわっていきまして、ようやくマラッカ海峡までたどりつきました。そこを掘り下げます。
マラッカ海峡なんですが、中国の唐が全盛期の時は、それほど栄えておりません。まあ、当然です。唐みたいな巨大国家が有り、治安もよくて通行税もないのなら、あえて危険な海のルートをたどる必要性は、あまりない・・・
あ、念のために書いておきます。必要性がないとはいっても、それでも海のルートは重要でして、それは何故かと言いますと、大量の貨物を運ぶ方法は前近代では船しかないのです。陸上の貨物輸送だと馬車しかないので、それだと船の積載量には負けてしまいます。
なので、必要性はあまりないとはいっても、それなりには繁栄していましたが、超大国「唐」の崩壊で海上輸送ルートはにわかに脚光を浴びます。陸上で小さな国家が乱立すると、通行税は取られるし、治安だって悪いし、なので良いことがあまりないのです。前近代の海は、領海という概念が薄いので、船さえ持ってたら好き勝手にどこまでも行けますし。
んー・・・多分ですが、船は中国の帆船でしょう。というのも、まだ西欧は十字軍で大騒ぎで海洋進出の準備がされてない。
どういう船かというと、wikiから参照。
「中国の帆船(8~18世紀)[編集]
北宋時代に高麗へ派遣する使節用として造られた帆船は全長約110メートル積載量1100トン以上で、見た事のない大船だと記される。一般の貿易船としては、積載量275トン程度の大船から万斛船と呼ばれる600~900トン程度の巨大帆船まで様々な種類の船が用いられた。戦闘船は速度が重視され、一日千里を航行すると記録されている。
ヴェネツィアの旅行家マルコ・ポーロ(Marco Polo,1254年 -1324年)は20年近く元朝のクビライ・ハーンに仕えた。そのときのことを口述した『東方見聞録』において、元朝の南方交易用の帆船は、4本のマストを持ち乗員は60名程度であること、竜骨(キール)によって船体は高い強度を保っていること、浸水しても沈没を免れる隔壁構造の船体を採用していること、羅針盤によって正確な遠洋航行が可能であることを報告している。
中国の明朝では鄭和が1405年から1433年にかけて7回の大航海を行った。航海した範囲は東南アジア、インド、アラビア半島、アフリカ東岸にまでわたった。これらの航海には長さ173m、幅56mにも及ぶ巨大な帆船が用いられた(詳細は項目「鄭和」を参照のこと)。」
そして、その時期にマラッカ海峡を治めていたのはマラッカ王国。マラッカ海峡はムラカとも言うそうです。ムラカ港務長官は四人いて、一人が中国などの東アジア担当、細かく言いますと、中国、琉球王国、チャンパ―を担当しておりました。
ほら、勝連貿易にたどり着いた(--d
マラッカ海峡を経由して勝連へと貿易していた可能性が高いです。そして、その中にローマ帝国コインも入っていた、と。
ちなみに後の話になりますが、マラッカ海峡は勝連が滅んだ1458年のあとの1511年にポルトガルが攻めてきて占拠され、ポルトガル海上帝国の主要拠点の一つにされます。でも、その前はマラッカ王国は繁栄していたと。
んー・・・そうだな、そうするか。
もう、ここまで書いてしまったので、開き直ってローマ帝国コイン発行の時代まで遡る事にします。
とんでもなく長いブログになってしまったな(笑)
今日はここまでにします。
朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
2016年11月27日
勝連城址の謎/ローマ帝国コインの発見3
さてと解体屋のおじさんです、こんばんわ。
今日はですね、先日に掲載した海のシルクロードの地図を見ながら、各地域の歴史をたどっていきたいと思いますが。
なぜ鄭和を持ち出したかと言いますと、鄭和の航海は第一次遠征が1404年なので勝連が滅びる前なのです。そして、近代以前の港町ってのは、ユンボウとかダンプとか有りませんので、手作業で町を建設しないといけませんから、港町ひとつ作るだけでもオオゴトになってしまうわけですよ。船員が陸に上がって娯楽を楽しみたいのに、町自体がなかったら航海のための食料すら確保できないという。
港町があるってことは、食料品や人の流通が確保されてて、なおかつ娯楽が有る・・・まあ、はっきり書きますと、売春宿ですか。男しかいない船から陸に上がると、男が真っ先に向かうところは、そういったところになりますね。そういうのを提供できる町がないと、船も立ち寄らないと。
というわけですので、先週に掲載した地図をもっかい掲載しまして、その地図をもとに各地域を巡っていきたいと思います。
(wiki(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E5%92%8C)より画像を拝借いたしました)

さて、まずは、鄭和の出発港の瀏河鎮から。
まずはwiki。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%80%89%E5%B8%82
えー、この試みは失敗だったかも・・・1458年以前の歴史は、wikiでも少ししか書いてないのな(^^;;
図書館に行って借りてくるしか方法ないかもだなあ・・・
ま、でも、一応抜粋すると「元の時に最も栄え、世界一の港だった」と書かれてありますので、1278年から1361年までが最盛期。勝連に行くには、ちょいと早すぎる時代ですね。多分、勝連には、そのころは城がないだろうし。ですが、鄭和は1404年で、そのころも港町なので、ローマ帝国コインが流入する有力な候補地の一つです。
次は長楽。福建省に位置しますので、福建省から抜粋。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%BB%BA%E7%9C%81
港町の部分を調べてみると、こういう記述が有りました。「海流の関係で日本に近く、近世には倭寇と結託して密貿易を行う福建人が多かった。」勝連が廃墟になるのは中世ですので、この記述だと倭寇が来るのはまだ早いですが、海流てきには大和に行けますので、ここも有力候補地の一つですね、はい。
そして、中国から離れてベトナムに行きます。クイニョンです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%B3
調べてみるとチャンパ王国の時代ですので、そっちのwikiにも飛びます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E7%8E%8B%E5%9B%BD
そして、この時代なんですが・・・物凄い戦乱の時代ですね。港町は滅んでないみたいですが、抜粋します。
「1402年、胡朝二世皇帝(胡漢蒼)が逆襲してチャンパの都を占領したが、ジャヤ・シンハヴァルマン5世が明に救援を求めたため、両国の抗争は明の永楽帝の干渉戦争(明胡戦争(英語版)、明・大虞戦争)を招くところとなり、1404年にマウラナ・マリク・イブラヒームはジャワ島のマジャパヒト王国に亡命し、その一族はワリ・サンガと呼ばれるようになった。1407年までに大虞胡朝は滅亡。1407年-1427年、第四次北属時期(英語版)。1408年にジャヤ・シンハヴァルマン5世は明の鄭和艦隊の訪問をクイニョンで受け歓待している。鄭和はマジャパヒト王国のスラバヤへも寄港している。
1418年-1428年、藍山蜂起。大越黎朝(黎初朝)の黎利による明軍撃退後、チャンパは南中部のヴィジャヤ王朝(英語版)(占城・闍槃:現クアンガイ省、ビンディン省)と中部南端のパーンドゥランガ王朝(ベトナム語版)(賓童龍・藩籠:現ニントゥアン省・ビントゥアン省)に分裂する形で再興された。チャム写本の『チャム王家年代記』は1433年に再興されたパーンドゥランガ王朝の系譜だけを記している。ヴィジャヤ王朝は1471年に黎聖宗の親征によって崩壊し(en:1471 Vietnamese invasion of Champa)、その故地であったアマラーヴァティー州、ヴィジャヤ州は大越に併合され、チャンパ王国の正統は中部南端のパーンドゥランガ王朝に移った。この時、ヴィジャヤ王槃羅茶全が、彼の息子シャー・パウ・リン(後のアリ・ムハヤット・シャー(英語版))をアチェの統治へと送り出したのがアチェ王国の始まりである。」
そういや、中国とベトナムは昔から戦争ばかりしていたな、と。この記述は勝連が滅ぶ前の話ですので、クイニョンは難民であふれてたかもしれない。大変な時期なわけです。
ここからローマ帝国コインも流入の可能性は有りますが、んー・・・船が来るから物流は有りますが、ベトナム人はローマ帝国コインをどうあつかっていたのかな?そこが少しわからないですね。有力ではないけど、候補地の一つかな。
さて、次に行きますと、スラバヤですね。インドネシアです。
ちょうど勝連貿易の時代には、インドネシアにはイスラム系のスルタン国が統治していたみたいなのですが・・・うん、wikiでも項目が作成されてない(汗)一応推測すると、港町は有りましたが、島国ですので、ローマ帝国コインが入ってきている可能性は低いかと思われます。いちおう頭にいれとこう、くらいかな?そして、次に行きますと。
パレンバン。こちらもインドネシアで島国ですね・・・えっと、シュリーヴィジャヤ王国というのが勝連貿易の時代に栄えていて、1414年にシュリーヴィジャヤ王国の最後の王子がイスラム教に改宗して、マラッカ王国の始まりになった、と書かれておりますので、その激動の時代に勝連の船がやってきたかもです。ふむ、ワクワクしますね。
そして次に行きますと、ようやくここまで来たか。
マラッカです。マラッカ海峡で有名なマラッカ。マレーシアですね。
とりあえずはwikiから。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%AB
そして、抜粋していきますと、香辛料貿易の中継港と栄えた・・・あー、来たかもな。ここは可能性がでかいぞ。西欧は香辛料を求めていて、ですが西欧には中世以前は輸出品がないので、ローマ帝国コインなどを代わりとして持たせて、香辛料を買っていた可能性が高い。
ポルトガルなどが占領するのは1511年で、勝連が廃墟になってからの話ですので、そっちは関係ないと。
うん、あと一回は勝連のブログを書かないといけないな。
今日はこれにて終了して、コーヒータイムします。
雑文、失礼いたしました。
では、また次回に宜しくお願い致します。
( ^^) _U~~
今日はですね、先日に掲載した海のシルクロードの地図を見ながら、各地域の歴史をたどっていきたいと思いますが。
なぜ鄭和を持ち出したかと言いますと、鄭和の航海は第一次遠征が1404年なので勝連が滅びる前なのです。そして、近代以前の港町ってのは、ユンボウとかダンプとか有りませんので、手作業で町を建設しないといけませんから、港町ひとつ作るだけでもオオゴトになってしまうわけですよ。船員が陸に上がって娯楽を楽しみたいのに、町自体がなかったら航海のための食料すら確保できないという。
港町があるってことは、食料品や人の流通が確保されてて、なおかつ娯楽が有る・・・まあ、はっきり書きますと、売春宿ですか。男しかいない船から陸に上がると、男が真っ先に向かうところは、そういったところになりますね。そういうのを提供できる町がないと、船も立ち寄らないと。
というわけですので、先週に掲載した地図をもっかい掲載しまして、その地図をもとに各地域を巡っていきたいと思います。
(wiki(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E5%92%8C)より画像を拝借いたしました)

さて、まずは、鄭和の出発港の瀏河鎮から。
まずはwiki。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%80%89%E5%B8%82
えー、この試みは失敗だったかも・・・1458年以前の歴史は、wikiでも少ししか書いてないのな(^^;;
図書館に行って借りてくるしか方法ないかもだなあ・・・
ま、でも、一応抜粋すると「元の時に最も栄え、世界一の港だった」と書かれてありますので、1278年から1361年までが最盛期。勝連に行くには、ちょいと早すぎる時代ですね。多分、勝連には、そのころは城がないだろうし。ですが、鄭和は1404年で、そのころも港町なので、ローマ帝国コインが流入する有力な候補地の一つです。
次は長楽。福建省に位置しますので、福建省から抜粋。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%BB%BA%E7%9C%81
港町の部分を調べてみると、こういう記述が有りました。「海流の関係で日本に近く、近世には倭寇と結託して密貿易を行う福建人が多かった。」勝連が廃墟になるのは中世ですので、この記述だと倭寇が来るのはまだ早いですが、海流てきには大和に行けますので、ここも有力候補地の一つですね、はい。
そして、中国から離れてベトナムに行きます。クイニョンです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%B3
調べてみるとチャンパ王国の時代ですので、そっちのwikiにも飛びます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E7%8E%8B%E5%9B%BD
そして、この時代なんですが・・・物凄い戦乱の時代ですね。港町は滅んでないみたいですが、抜粋します。
「1402年、胡朝二世皇帝(胡漢蒼)が逆襲してチャンパの都を占領したが、ジャヤ・シンハヴァルマン5世が明に救援を求めたため、両国の抗争は明の永楽帝の干渉戦争(明胡戦争(英語版)、明・大虞戦争)を招くところとなり、1404年にマウラナ・マリク・イブラヒームはジャワ島のマジャパヒト王国に亡命し、その一族はワリ・サンガと呼ばれるようになった。1407年までに大虞胡朝は滅亡。1407年-1427年、第四次北属時期(英語版)。1408年にジャヤ・シンハヴァルマン5世は明の鄭和艦隊の訪問をクイニョンで受け歓待している。鄭和はマジャパヒト王国のスラバヤへも寄港している。
1418年-1428年、藍山蜂起。大越黎朝(黎初朝)の黎利による明軍撃退後、チャンパは南中部のヴィジャヤ王朝(英語版)(占城・闍槃:現クアンガイ省、ビンディン省)と中部南端のパーンドゥランガ王朝(ベトナム語版)(賓童龍・藩籠:現ニントゥアン省・ビントゥアン省)に分裂する形で再興された。チャム写本の『チャム王家年代記』は1433年に再興されたパーンドゥランガ王朝の系譜だけを記している。ヴィジャヤ王朝は1471年に黎聖宗の親征によって崩壊し(en:1471 Vietnamese invasion of Champa)、その故地であったアマラーヴァティー州、ヴィジャヤ州は大越に併合され、チャンパ王国の正統は中部南端のパーンドゥランガ王朝に移った。この時、ヴィジャヤ王槃羅茶全が、彼の息子シャー・パウ・リン(後のアリ・ムハヤット・シャー(英語版))をアチェの統治へと送り出したのがアチェ王国の始まりである。」
そういや、中国とベトナムは昔から戦争ばかりしていたな、と。この記述は勝連が滅ぶ前の話ですので、クイニョンは難民であふれてたかもしれない。大変な時期なわけです。
ここからローマ帝国コインも流入の可能性は有りますが、んー・・・船が来るから物流は有りますが、ベトナム人はローマ帝国コインをどうあつかっていたのかな?そこが少しわからないですね。有力ではないけど、候補地の一つかな。
さて、次に行きますと、スラバヤですね。インドネシアです。
ちょうど勝連貿易の時代には、インドネシアにはイスラム系のスルタン国が統治していたみたいなのですが・・・うん、wikiでも項目が作成されてない(汗)一応推測すると、港町は有りましたが、島国ですので、ローマ帝国コインが入ってきている可能性は低いかと思われます。いちおう頭にいれとこう、くらいかな?そして、次に行きますと。
パレンバン。こちらもインドネシアで島国ですね・・・えっと、シュリーヴィジャヤ王国というのが勝連貿易の時代に栄えていて、1414年にシュリーヴィジャヤ王国の最後の王子がイスラム教に改宗して、マラッカ王国の始まりになった、と書かれておりますので、その激動の時代に勝連の船がやってきたかもです。ふむ、ワクワクしますね。
そして次に行きますと、ようやくここまで来たか。
マラッカです。マラッカ海峡で有名なマラッカ。マレーシアですね。
とりあえずはwikiから。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%AB
そして、抜粋していきますと、香辛料貿易の中継港と栄えた・・・あー、来たかもな。ここは可能性がでかいぞ。西欧は香辛料を求めていて、ですが西欧には中世以前は輸出品がないので、ローマ帝国コインなどを代わりとして持たせて、香辛料を買っていた可能性が高い。
ポルトガルなどが占領するのは1511年で、勝連が廃墟になってからの話ですので、そっちは関係ないと。
うん、あと一回は勝連のブログを書かないといけないな。
今日はこれにて終了して、コーヒータイムします。
雑文、失礼いたしました。
では、また次回に宜しくお願い致します。
( ^^) _U~~
2016年11月06日
勝連城址の謎/ローマ帝国コインの発見2
さてと解体屋のおじさんです、こんばんは。
本日は勝連城址で発見されたローマ帝国コインの謎を追いかけたいと思いますが。
まずですね、以下の記事をご覧ください。
http://fundo.jp/96701
この記事に書いてあるように1458年に勝連は廃墟が確定、そうすると阿麻和利当代か、それ以前の話になりました。
とすると、日本に宣教師が来てウロウロは1549年以降なので、九州のキリスト教文化とは関係が無くなったのは、ほぼ確実になりました。
ちなみにこの時期に西欧は何していたのかというと、十字軍です。
西欧ではトルコのオスマン帝国が台頭してビザンツ帝国(東ローマ帝国)が倒されたため、教皇ビウス二世がオスマン帝国打倒のため十字軍編成を各国に呼びかけていた時期で、宣教師を派遣している暇がないのですね。
というか、オスマン帝国が西欧が東に向かわないように蓋の役目を果たしてしまったので、それで西欧は海に活路を求めたわけです。でも、それは後の話になりまして、勝連のローマ帝国コインの話とは関係は無い模様です。
なので・・・他のルートを模索しようと考えたら、FB友達がサトウキビルートはどう?と仰られました。
あー、サトウキビだと新大陸の商品以前の話だから、それは有りかも?という事で、沖縄伝来のルーツを探ってみました。たしか、鑑真さんが砂糖を薬として日本に持ち込んだのが平安時代の825年だったような・・・?いけるかな?
大陸貿易が盛んになった鎌倉時代末期だとヤマトは積極的に砂糖を輸入していたみたいですが、モンゴル帝国台頭の時代で元寇も有るので微妙・・・元寇が行われたのは1274年と1281年度・・・
ちょいと元の記事をたどってみると、勝連の貿易が盛んになったのは、14世紀から15世紀なので・・・・貿易が活発になったのが十四世紀初めの1301年からでも噛み合わない・・・
ちなみにサトウキビの栽培を沖縄が始めたのは、ずっと後の1623年でして。
1623年に琉球の儀間真常が中国に使いを出し、砂糖の製造方法を学ばせ黒糖を製造したと言われています。
1623年の時代は、もう江戸時代に入っていて、徳川秀忠、家光の時代です。
そして、もう一つ書いておかないといけないのは中国ルートでして、中国の明は1372年に洪武帝が海禁令を出したため・・・あ、特定できたかも?1301年には勝連は築城されており貿易も行っておりましたので、明の海禁令が発令する1372年との間に、ローマ帝国コインが流入してきた可能性が高い。あと、当時の中国と中国人は装飾品として形が崩れたローマ帝国コインを取り扱っておりましたので、勝連の阿麻和利や、阿麻和利を滅ぼした金丸は気にしなかくて見逃した可能性が高い。
ふむ・・・いろいろと推論を重ねてみるものです。だいたい噛み合った。
明は朝貢貿易のみを正統な貿易として規制したので、中国では密貿易が横行することになります。なので、阿麻和利当代の時代にも入ってきた可能性も高いです。
ですけど、1458年以降は廃墟なため、そのあとに流入してきた可能性は、かなり低い・・・物見遊山な観光客が廃墟な勝連にきて落としてしまったとかなら、ありえなくもないけれど・・・ま、それくらいな可能性が低い話になります。
そして、ラストな海のシルクロードですが。
とりあえずwikiから抜粋。
「中国の南から海に乗り出し、東シナ海、南シナ海、インド洋を経てインドへ、さらにアラビア半島へと至る海路は「海のシルクロード」とも呼ばれる。」
ただ、さきほども述べたとおり、勝連が築城されて貿易を行い始めたのは、どんなに早くても1301年からで、1458年以降は廃墟確定だから、その時代の海のシルクロードになりますが。
明の洪武帝が「下海禁止令」を出して民間の貿易を禁じた後に、宦官の鄭和に朝貢貿易を諸外国に促すよう大艦隊を建築して送り出します。そして、鄭和がたどり着いた港が下記の画像で、こちら。
(wiki(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E5%92%8C)より画像を拝借いたしました)

海流というのはいつの時代になってもほぼ変わらないはずなので、この鄭和が寄港した港とその国々の歴史を紐解けば、勝連のローマ帝国コインの謎がとける可能性が高くなります。
ま、でも、この様子だと中国ルートの可能性が高いかもです。
さて、本日はこれにて終了します。
朝のコーヒータイム、お先に失礼します。
( ^^) _U~~
本日は勝連城址で発見されたローマ帝国コインの謎を追いかけたいと思いますが。
まずですね、以下の記事をご覧ください。
http://fundo.jp/96701
この記事に書いてあるように1458年に勝連は廃墟が確定、そうすると阿麻和利当代か、それ以前の話になりました。
とすると、日本に宣教師が来てウロウロは1549年以降なので、九州のキリスト教文化とは関係が無くなったのは、ほぼ確実になりました。
ちなみにこの時期に西欧は何していたのかというと、十字軍です。
西欧ではトルコのオスマン帝国が台頭してビザンツ帝国(東ローマ帝国)が倒されたため、教皇ビウス二世がオスマン帝国打倒のため十字軍編成を各国に呼びかけていた時期で、宣教師を派遣している暇がないのですね。
というか、オスマン帝国が西欧が東に向かわないように蓋の役目を果たしてしまったので、それで西欧は海に活路を求めたわけです。でも、それは後の話になりまして、勝連のローマ帝国コインの話とは関係は無い模様です。
なので・・・他のルートを模索しようと考えたら、FB友達がサトウキビルートはどう?と仰られました。
あー、サトウキビだと新大陸の商品以前の話だから、それは有りかも?という事で、沖縄伝来のルーツを探ってみました。たしか、鑑真さんが砂糖を薬として日本に持ち込んだのが平安時代の825年だったような・・・?いけるかな?
大陸貿易が盛んになった鎌倉時代末期だとヤマトは積極的に砂糖を輸入していたみたいですが、モンゴル帝国台頭の時代で元寇も有るので微妙・・・元寇が行われたのは1274年と1281年度・・・
ちょいと元の記事をたどってみると、勝連の貿易が盛んになったのは、14世紀から15世紀なので・・・・貿易が活発になったのが十四世紀初めの1301年からでも噛み合わない・・・
ちなみにサトウキビの栽培を沖縄が始めたのは、ずっと後の1623年でして。
1623年に琉球の儀間真常が中国に使いを出し、砂糖の製造方法を学ばせ黒糖を製造したと言われています。
1623年の時代は、もう江戸時代に入っていて、徳川秀忠、家光の時代です。
そして、もう一つ書いておかないといけないのは中国ルートでして、中国の明は1372年に洪武帝が海禁令を出したため・・・あ、特定できたかも?1301年には勝連は築城されており貿易も行っておりましたので、明の海禁令が発令する1372年との間に、ローマ帝国コインが流入してきた可能性が高い。あと、当時の中国と中国人は装飾品として形が崩れたローマ帝国コインを取り扱っておりましたので、勝連の阿麻和利や、阿麻和利を滅ぼした金丸は気にしなかくて見逃した可能性が高い。
ふむ・・・いろいろと推論を重ねてみるものです。だいたい噛み合った。
明は朝貢貿易のみを正統な貿易として規制したので、中国では密貿易が横行することになります。なので、阿麻和利当代の時代にも入ってきた可能性も高いです。
ですけど、1458年以降は廃墟なため、そのあとに流入してきた可能性は、かなり低い・・・物見遊山な観光客が廃墟な勝連にきて落としてしまったとかなら、ありえなくもないけれど・・・ま、それくらいな可能性が低い話になります。
そして、ラストな海のシルクロードですが。
とりあえずwikiから抜粋。
「中国の南から海に乗り出し、東シナ海、南シナ海、インド洋を経てインドへ、さらにアラビア半島へと至る海路は「海のシルクロード」とも呼ばれる。」
ただ、さきほども述べたとおり、勝連が築城されて貿易を行い始めたのは、どんなに早くても1301年からで、1458年以降は廃墟確定だから、その時代の海のシルクロードになりますが。
明の洪武帝が「下海禁止令」を出して民間の貿易を禁じた後に、宦官の鄭和に朝貢貿易を諸外国に促すよう大艦隊を建築して送り出します。そして、鄭和がたどり着いた港が下記の画像で、こちら。
(wiki(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%84%AD%E5%92%8C)より画像を拝借いたしました)

海流というのはいつの時代になってもほぼ変わらないはずなので、この鄭和が寄港した港とその国々の歴史を紐解けば、勝連のローマ帝国コインの謎がとける可能性が高くなります。
ま、でも、この様子だと中国ルートの可能性が高いかもです。
さて、本日はこれにて終了します。
朝のコーヒータイム、お先に失礼します。
( ^^) _U~~
2016年10月02日
勝連城址の謎/ローマ帝国コインの発見1
さてと解体屋のおじさんです、おはようございます。
本日は中山世鑑の続きを書こうと思っておりましたが、予定を変更して勝連城址で見つかったローマ帝国コインの推論に切り替えたいと思います。
なぜ、いきなりそうなるかと申しますと、自分のFB友達に内地の方がいらっしゃいまして、勝連城址/ローマ帝国と大分県のキリスト教文化に繋がりがないか?と尋ねられてきたわけです。
その時は仕事中だったんだけど、記憶を頼りにパパパと調べた結果、
勝連を発展させた阿麻和利は1458年没で、ときの将軍は足利義政、
フランシスコザビエルの来日は1549年で日本は戦国時代に突入、ときの将軍は足利義晴、三好家が京都をウロウロと。
年代がずれまくりーーーー(汗)
さらに年代のことを言ったら、ローマ帝国コインは三世紀、四世紀のものだから・・・
勝連が発展したのは阿麻和利以降の話で、阿麻和利以前は何もないよな・・・城は有ったし貿易はしていたみたいだけど・・・
築城は12世紀と13世紀のもの・・・ふむ?
阿麻和利は築城された城を根拠地として貿易を開始、「麒麟児」と呼ばれるにいたるわけです。
(麒麟とは天子が現れた時に出現する聖獣)
さらに阿麻和利を倒した金丸は、この後に就任するのは国王取次の御物城御鎖側官(貿易長官)で、
全てにおいてそつがない金丸が琉球王国内の貿易を掌握して、ローマ帝国コインを見逃すというミスするかなあ・・・?
いや、金丸も人間だからミスはするか・・・?
なんで勝連に三世紀のローマ帝国コイン有るのかわからないーーーー、なんで琉球国王に献上しないんだよーーーーー?阿麻和利亡くなって金丸が貿易長官なのに、隠してたのかよ、勝連ーーーーー?
になっておりましたので、とりあえず元記事みようと検索。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/09/27/okinawa-rome-coin_n_12224262.html
フム・・・外見を見ると劣化しているので、この状態なら沖縄に入ってきても、金丸や阿麻和利がスルーしてしまった、って言うことも有ると判断しました。というわけですので、チート人物二人のミス説は無くなりました。
そして、見逃し説がとられるなら、阿麻和利以前も貿易してたので、その時代の東南アジアからの流入の可能性が高くなります。他にも逆に、この時代以降に入ってきた可能性も高くなりますが・・・首里王府の御物城御鎖側官な金丸が貿易を掌握した後に、小さいとはいえ商品なコインをスルーするとは考えにくい・・・という事は、阿麻和利以前だ。それだ!そこの歴史を掘り下げよう。
まずは中国なんですが、明の永楽帝は勘合貿易のみを行い(朝貢貿易)ほかの貿易は禁止していたので、冊封体制な琉球は勘合貿易でコインが入ってきたなら首里城で見つからないといけないので、中国を中心とした陸のシルクロードは8割がた無し、になります。
次の西欧からの海を渡っての流入ですが、宣教師が日本でウロウロしはじめたのが1549年、そのころには琉球王国は勝連も含めて国内の貿易を掌握してたので、首里城に献上されてないとおかしい・・・
ま、ただ、単に見逃しただけ・・・という推論は、さっきも言いましたが・・・・
という事なので、これもなし、
ということは、阿麻和利以前か阿麻和利の当代の時代に東南アジアとの貿易で入手の可能性が高い・・・いわゆる海のシルクロード、それも1458年以前の東南アジアルート。
よし、きた。色々と検証を重ねた結果、たどり着いた。
1458年以前の勝連の歴史と貿易を行ってきた国をあげれば、道筋が解るぞっ(^^d
というわけで、1458年以前の東南アジアの歴史と、勝連の歴史は来週に回したいと思います。
本日はこれまで、朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
本日は中山世鑑の続きを書こうと思っておりましたが、予定を変更して勝連城址で見つかったローマ帝国コインの推論に切り替えたいと思います。
なぜ、いきなりそうなるかと申しますと、自分のFB友達に内地の方がいらっしゃいまして、勝連城址/ローマ帝国と大分県のキリスト教文化に繋がりがないか?と尋ねられてきたわけです。
その時は仕事中だったんだけど、記憶を頼りにパパパと調べた結果、
勝連を発展させた阿麻和利は1458年没で、ときの将軍は足利義政、
フランシスコザビエルの来日は1549年で日本は戦国時代に突入、ときの将軍は足利義晴、三好家が京都をウロウロと。
年代がずれまくりーーーー(汗)
さらに年代のことを言ったら、ローマ帝国コインは三世紀、四世紀のものだから・・・
勝連が発展したのは阿麻和利以降の話で、阿麻和利以前は何もないよな・・・城は有ったし貿易はしていたみたいだけど・・・
築城は12世紀と13世紀のもの・・・ふむ?
阿麻和利は築城された城を根拠地として貿易を開始、「麒麟児」と呼ばれるにいたるわけです。
(麒麟とは天子が現れた時に出現する聖獣)
さらに阿麻和利を倒した金丸は、この後に就任するのは国王取次の御物城御鎖側官(貿易長官)で、
全てにおいてそつがない金丸が琉球王国内の貿易を掌握して、ローマ帝国コインを見逃すというミスするかなあ・・・?
いや、金丸も人間だからミスはするか・・・?
なんで勝連に三世紀のローマ帝国コイン有るのかわからないーーーー、なんで琉球国王に献上しないんだよーーーーー?阿麻和利亡くなって金丸が貿易長官なのに、隠してたのかよ、勝連ーーーーー?
になっておりましたので、とりあえず元記事みようと検索。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/09/27/okinawa-rome-coin_n_12224262.html
フム・・・外見を見ると劣化しているので、この状態なら沖縄に入ってきても、金丸や阿麻和利がスルーしてしまった、って言うことも有ると判断しました。というわけですので、チート人物二人のミス説は無くなりました。
そして、見逃し説がとられるなら、阿麻和利以前も貿易してたので、その時代の東南アジアからの流入の可能性が高くなります。他にも逆に、この時代以降に入ってきた可能性も高くなりますが・・・首里王府の御物城御鎖側官な金丸が貿易を掌握した後に、小さいとはいえ商品なコインをスルーするとは考えにくい・・・という事は、阿麻和利以前だ。それだ!そこの歴史を掘り下げよう。
まずは中国なんですが、明の永楽帝は勘合貿易のみを行い(朝貢貿易)ほかの貿易は禁止していたので、冊封体制な琉球は勘合貿易でコインが入ってきたなら首里城で見つからないといけないので、中国を中心とした陸のシルクロードは8割がた無し、になります。
次の西欧からの海を渡っての流入ですが、宣教師が日本でウロウロしはじめたのが1549年、そのころには琉球王国は勝連も含めて国内の貿易を掌握してたので、首里城に献上されてないとおかしい・・・
ま、ただ、単に見逃しただけ・・・という推論は、さっきも言いましたが・・・・
という事なので、これもなし、
ということは、阿麻和利以前か阿麻和利の当代の時代に東南アジアとの貿易で入手の可能性が高い・・・いわゆる海のシルクロード、それも1458年以前の東南アジアルート。
よし、きた。色々と検証を重ねた結果、たどり着いた。
1458年以前の勝連の歴史と貿易を行ってきた国をあげれば、道筋が解るぞっ(^^d
というわけで、1458年以前の東南アジアの歴史と、勝連の歴史は来週に回したいと思います。
本日はこれまで、朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
2016年09月11日
琉球王国史と日本史の比較/尚巴志の軌跡5
さてと解体屋のおじさんです、今晩は。
夜半に目が覚めましたので、ブログ書きたいと思いますが。
ちょいと、かるく日本史と琉球王国史を比較していきたいと思います。
ただねえ・・・今、資料に当たったところ、
「中山世鑑」と漢文で制作された「中山世譜」で記述が違うのですよ。
ただ、永楽20年(1422年)に尚巴志の即位か三山統一、というのは確定みたいなので、そこから話を進めていきますが。
その1422年ですが。
45年後の1467年に日本(ヤマト)では応仁の乱なので、戦国時代が先に終わってしまったのですね、沖縄は。
室町将軍は第4代 足利義持。
えー、どうしましょ?義満が南北朝の合一に成功して、室町幕府の安定期の時期ですねえ。
惣領制もこの時期には問題は、あまりないし。
内地はこの時期は守護領国制と惣領制と荘園制も土地問題は複雑ですが、特に混乱は無いです。
問題は沖縄。
沖縄は各地の豪族(按司)の連合国家ってことでOKなのかなあ?
内地のような、荘園出来て武士の政権(幕府)が介入とか、そういうことはないのです。
あえてこの時期をヤマトで例えるなら、大化の改新以前の蘇我氏と物部氏の争いとか、そういう時代で、
尚巴志がその争いに勝った、というところですね。
そして前回の山北王との戦いに出てきた宝刀「千代金丸」ですが、このまま尚氏の家宝となります。
どんな刀なのかな?とウィキで調べたところ、内地風の日本刀とのことです。
そして平安時代後期には日本刀は作られていたので、大和と沖縄は既に交流が有ったという傍証になると思います。
冊封体制に入りながらも言葉は大和の古語であり着るものも着物ですので、日中の文化が入り混じって独特な文化に成熟していったという事ですね。
ただ、沖縄を中華風に思いっきり傾けたのは薩摩です。
薩摩は中華の属国も支配しているぞ、という幕府に対する示威行為。そして冊封体制の貿易の利を独占するため。
そのため、反ヤマトの空気も沖縄には有ります。
でもね、自分はあえて言いますと、もうそんな時代じゃない、と。
日本は民主主義国家であり、法の下の平等を体現した国でもある。すなわち法治国家。
沖縄も法治国家に属して成長してきた。
法の上に人を置く、人治国家の中国とは相容れないのです。
人治国家の危険性は、別の機会に語りたいと思います。
さて、今日の語り部は終了といたします。
朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
夜半に目が覚めましたので、ブログ書きたいと思いますが。
ちょいと、かるく日本史と琉球王国史を比較していきたいと思います。
ただねえ・・・今、資料に当たったところ、
「中山世鑑」と漢文で制作された「中山世譜」で記述が違うのですよ。
ただ、永楽20年(1422年)に尚巴志の即位か三山統一、というのは確定みたいなので、そこから話を進めていきますが。
その1422年ですが。
45年後の1467年に日本(ヤマト)では応仁の乱なので、戦国時代が先に終わってしまったのですね、沖縄は。
室町将軍は第4代 足利義持。
えー、どうしましょ?義満が南北朝の合一に成功して、室町幕府の安定期の時期ですねえ。
惣領制もこの時期には問題は、あまりないし。
内地はこの時期は守護領国制と惣領制と荘園制も土地問題は複雑ですが、特に混乱は無いです。
問題は沖縄。
沖縄は各地の豪族(按司)の連合国家ってことでOKなのかなあ?
内地のような、荘園出来て武士の政権(幕府)が介入とか、そういうことはないのです。
あえてこの時期をヤマトで例えるなら、大化の改新以前の蘇我氏と物部氏の争いとか、そういう時代で、
尚巴志がその争いに勝った、というところですね。
そして前回の山北王との戦いに出てきた宝刀「千代金丸」ですが、このまま尚氏の家宝となります。
どんな刀なのかな?とウィキで調べたところ、内地風の日本刀とのことです。
そして平安時代後期には日本刀は作られていたので、大和と沖縄は既に交流が有ったという傍証になると思います。
冊封体制に入りながらも言葉は大和の古語であり着るものも着物ですので、日中の文化が入り混じって独特な文化に成熟していったという事ですね。
ただ、沖縄を中華風に思いっきり傾けたのは薩摩です。
薩摩は中華の属国も支配しているぞ、という幕府に対する示威行為。そして冊封体制の貿易の利を独占するため。
そのため、反ヤマトの空気も沖縄には有ります。
でもね、自分はあえて言いますと、もうそんな時代じゃない、と。
日本は民主主義国家であり、法の下の平等を体現した国でもある。すなわち法治国家。
沖縄も法治国家に属して成長してきた。
法の上に人を置く、人治国家の中国とは相容れないのです。
人治国家の危険性は、別の機会に語りたいと思います。
さて、今日の語り部は終了といたします。
朝のコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
2016年08月21日
決戦!中山王対山北王(後編)/尚巴志の軌跡4
さてと解体屋のおじさんです、こんばんは。
本日も夜半に目が覚めましたので、ブログの続きを書きたいと思います。
というか、ここからは中山世鑑も戦いのシーンだらけです。
司馬遷(歴史書「史記」の著作者)に及びもつかないとか書きながら、羽地朝秀氏のりまくっております。
司馬遷と言えば、故司馬遼太郎氏のペンネームも「(司馬)遷に(遥)かに及ばない、日本人だから(太郎)」の中のカッコ文字を取って付けたとは有名な話です。
話がそれました、元に戻しますと・・・中山世鑑から引用。書くか
長くなりますよ、いきます。今帰仁城での決戦です。
「三月十三日、合図の時刻となり、正面から背後から合計三千機が城の麓へ押し寄せ、楯の端を叩いてとき閔の声を上げると、山をも崩し地軸さえも砕かんばかりであった。
城の様子を見ると流石に峻険堅固であり、二重三重に鹿垣を巡らし先のとがった丸太をびっしりと設置して防御していた。屈強の射手と思われる兵士が兜を輝かし、鏃を揃えて待ちかまえ、寄せ手全く攻め入るスキがなかった。」
長くなりますよ。浦添按司の激励。
「逆徒どもが堅固な城を頼んでいることは先刻承知のことなのだ。逆徒を滅ぼすためにこの地に来たわれらが、難攻の城に立てこもる敵をただ漫然と見守って時を失するなら、背後の味方に遅れを取って臆病を笑われてしまうぞ。者ども、あの防御柵を引き破り、臨機応変に攻撃せよ」
話の流れとしましては、このあと、防御柵を攻めて側が突破し攻め入ろうとしたところ、敵は鏃を揃えて雨のように矢を射かけて大半を打ち取られた。ですが攻めて側の戦力の逐次投入により矢が足りなくなり、太刀や長刀の切り先を並べて押し出してきた。
今帰仁城外での決戦になりますね。両者ともに孫呉の兵法、大公房、張良の術策を知っておりますので、魚鱗の陣形、鶴翼の陣形にひらいて、時には攻め、時には攻め入られました。
えー、昼夜三日の大激戦になりました。山北王、マジ強い(^^;;
多分攻めてたのは総司令官は護佐丸、護佐丸に3000も与えて、なのに300でこんなに粘るのか、この山北王は(^^;;
そのため羽地按司は城の南西は攻め入りにくいため、20人ほどまわして火をかけて退路を断ち鬨の声を上げさせて、これと同時に正面と背後から同時に攻めようとの提案、護佐丸は受け入れまして指示を出しました。
兵士20名が城の南西に近寄ってみると、予想通り誰もいなかったので、火を放ち鬨の声をあげました。その時の声と同時に全軍突撃したため、山北王がわの兵士たちは「これまでだ」と四方八方に逃げ散りました。
ようやく勝てたと思いますが、まだ山北王が残っております。
山北王は「今はこれまでだ。もう一度最後の合戦をして、潔く自害しよう」
んー・・・信長なら負けても逃げますね。信長は主君さえ打ち取られなければ、再起を図れることを知っておりますので。足利尊氏などもそうですね。そこらへんは、一歩及ばずかなあ、山北王も。ま、でも、勇者ですよ。
山北王は赤地錦の直垂に、緋おどしの鎧をつけ、龍頭の兜の緒をしめ、先祖伝来の宝刀「千代金丸」を腰にはき、三尺五寸の小長刀をわきに抱えて、17騎で3000騎に突撃・・・
おいおいおい・・・如何にも大将という格好して突撃するの・・・?(汗)
ただし、めっちゃ強いです。項羽並の強さ。
17騎で3000騎を後退させやがった(笑)お前は上杉謙信か(^^;
上杉謙信という不思議な男は、2000兵士いたら20000兵でも戦えるという、信じられない強さだったそうですが、この方もそうだなあ(^^;;
あまりにも強いので護佐丸側は弓で射かけます。なので山北王はいったん引いて城にこもり、
「むやみに罪を作っても何もならない。しかし人手にかかるのも末代までの恥だ」として、
二の丸にあがった。
二の丸には大昔から城を守護する「イベ」として崇め奉ってた岩があった。その前で「さあ、イベも、そしてイベにおわす神も共に冥土に旅立ちましょう」と言って切腹された。
引き抜いた刀でイベの岩も切り裂いて、その刀を後ろざまへ五町あまりの重間川に投げ入れられた。これを見た七騎の手勢も、次々に自害して主君の屍に重なり合った。
山北王は自立して以来、100有余年もの間、中山王と七十回も戦いましたが中山王を退けてきた。
ですが、ようやく倒せたわけですが・・・中山世鑑に書かれてある通り、この名もなき山北王は大勇者ですね。
兵力差10倍で一歩も引かなかった。
後世に知らしめる価値が有ります。時間ある時に今帰仁城址に行ってきます。
さて、ようやく三山統一まで書けました。
これにて今日の語り部は終了、朝のコーヒータイム、お疲れです。
( ^^) _U~~
本日も夜半に目が覚めましたので、ブログの続きを書きたいと思います。
というか、ここからは中山世鑑も戦いのシーンだらけです。
司馬遷(歴史書「史記」の著作者)に及びもつかないとか書きながら、羽地朝秀氏のりまくっております。
司馬遷と言えば、故司馬遼太郎氏のペンネームも「(司馬)遷に(遥)かに及ばない、日本人だから(太郎)」の中のカッコ文字を取って付けたとは有名な話です。
話がそれました、元に戻しますと・・・中山世鑑から引用。書くか
長くなりますよ、いきます。今帰仁城での決戦です。
「三月十三日、合図の時刻となり、正面から背後から合計三千機が城の麓へ押し寄せ、楯の端を叩いてとき閔の声を上げると、山をも崩し地軸さえも砕かんばかりであった。
城の様子を見ると流石に峻険堅固であり、二重三重に鹿垣を巡らし先のとがった丸太をびっしりと設置して防御していた。屈強の射手と思われる兵士が兜を輝かし、鏃を揃えて待ちかまえ、寄せ手全く攻め入るスキがなかった。」
長くなりますよ。浦添按司の激励。
「逆徒どもが堅固な城を頼んでいることは先刻承知のことなのだ。逆徒を滅ぼすためにこの地に来たわれらが、難攻の城に立てこもる敵をただ漫然と見守って時を失するなら、背後の味方に遅れを取って臆病を笑われてしまうぞ。者ども、あの防御柵を引き破り、臨機応変に攻撃せよ」
話の流れとしましては、このあと、防御柵を攻めて側が突破し攻め入ろうとしたところ、敵は鏃を揃えて雨のように矢を射かけて大半を打ち取られた。ですが攻めて側の戦力の逐次投入により矢が足りなくなり、太刀や長刀の切り先を並べて押し出してきた。
今帰仁城外での決戦になりますね。両者ともに孫呉の兵法、大公房、張良の術策を知っておりますので、魚鱗の陣形、鶴翼の陣形にひらいて、時には攻め、時には攻め入られました。
えー、昼夜三日の大激戦になりました。山北王、マジ強い(^^;;
多分攻めてたのは総司令官は護佐丸、護佐丸に3000も与えて、なのに300でこんなに粘るのか、この山北王は(^^;;
そのため羽地按司は城の南西は攻め入りにくいため、20人ほどまわして火をかけて退路を断ち鬨の声を上げさせて、これと同時に正面と背後から同時に攻めようとの提案、護佐丸は受け入れまして指示を出しました。
兵士20名が城の南西に近寄ってみると、予想通り誰もいなかったので、火を放ち鬨の声をあげました。その時の声と同時に全軍突撃したため、山北王がわの兵士たちは「これまでだ」と四方八方に逃げ散りました。
ようやく勝てたと思いますが、まだ山北王が残っております。
山北王は「今はこれまでだ。もう一度最後の合戦をして、潔く自害しよう」
んー・・・信長なら負けても逃げますね。信長は主君さえ打ち取られなければ、再起を図れることを知っておりますので。足利尊氏などもそうですね。そこらへんは、一歩及ばずかなあ、山北王も。ま、でも、勇者ですよ。
山北王は赤地錦の直垂に、緋おどしの鎧をつけ、龍頭の兜の緒をしめ、先祖伝来の宝刀「千代金丸」を腰にはき、三尺五寸の小長刀をわきに抱えて、17騎で3000騎に突撃・・・
おいおいおい・・・如何にも大将という格好して突撃するの・・・?(汗)
ただし、めっちゃ強いです。項羽並の強さ。
17騎で3000騎を後退させやがった(笑)お前は上杉謙信か(^^;
上杉謙信という不思議な男は、2000兵士いたら20000兵でも戦えるという、信じられない強さだったそうですが、この方もそうだなあ(^^;;
あまりにも強いので護佐丸側は弓で射かけます。なので山北王はいったん引いて城にこもり、
「むやみに罪を作っても何もならない。しかし人手にかかるのも末代までの恥だ」として、
二の丸にあがった。
二の丸には大昔から城を守護する「イベ」として崇め奉ってた岩があった。その前で「さあ、イベも、そしてイベにおわす神も共に冥土に旅立ちましょう」と言って切腹された。
引き抜いた刀でイベの岩も切り裂いて、その刀を後ろざまへ五町あまりの重間川に投げ入れられた。これを見た七騎の手勢も、次々に自害して主君の屍に重なり合った。
山北王は自立して以来、100有余年もの間、中山王と七十回も戦いましたが中山王を退けてきた。
ですが、ようやく倒せたわけですが・・・中山世鑑に書かれてある通り、この名もなき山北王は大勇者ですね。
兵力差10倍で一歩も引かなかった。
後世に知らしめる価値が有ります。時間ある時に今帰仁城址に行ってきます。
さて、ようやく三山統一まで書けました。
これにて今日の語り部は終了、朝のコーヒータイム、お疲れです。
( ^^) _U~~
2016年08月07日
決戦!中山王対山北王(前編)/尚巴志の軌跡3
さてと解体屋のおじさんです、こんばんは。
時刻は夜半三時半ですが、ブログを書きたいと思います。
そして、いきなりですが中山世鑑からの抜粋。
「今の人々の多くは心変わりして、我が方は小勢となったが、多勢を恐れて一戦もせずに降参するのは如何にも口惜しいことだ。そして、山北国をうち建てた祖先に恥をさらすことになる。さあ、中山の軍は攻め寄せてくるがよい。これを一蹴して手柄を見せようではないか。攻め寄せる中山軍が例え数万騎あろうと、これを打ち破るのは造作もないことだ。もし命運尽きて、この戦に敗れるようなことが有れば、その時は潔く自害して、名を後世に残そうぞ。さあ者共、支度をせよ。怖気づいて笑いものになるな」
・・・沖縄にも項羽がいた・・・
いや、ちょいまて。いくらなんでも、この気負いは半端なさすぎでしょ。なんだ、このラスボス感。
ちなみに、項羽は漢楚争覇時代の楚の英雄でして、あまりにも強すぎて誰も勝てなかったんですよ。ですが、軍師張良が包囲網を作って、さらに偽りの講和を持ちかけて受けさせて、その講和を破って攻めるということで、ようやく倒せたという、ものすごいチートな英雄でした。
尚巴志にも、もうこの時期には護佐丸とかも臣下にいますけどね。
でも、ものすごく芯がしっかりした気構え。手ごわいですな。
さて、先に進みます。
尚巴志はいくら山北王が勇者でも、そのうち降参するとみていたのですが、羽地按司が飛脚を飛ばして言上。
「山北王は今は小勢ですが、残りとどまった一騎当千のつわものが、なお三百騎あります。これらを率いて謀反を企てて城にたてこもり、近隣の兵を集めて首里にのぼろうと準備をしております。急いで官軍を遣わして討伐しなければ、由々しき事態となるでしょう」
というわけで、中山王は浦添按司、越来按司、読谷山按司を大将とする二千騎を討手として差し向けた。
そして名護にたどり着くと軍を二手に分けました。越来按司と読谷山按司が背後を責める大将として名護按司を道案内に800騎が山路から山北城に向かいます。
さらに浦添按司、国頭按司、羽地按司を正面の大将として2700騎が羽地の寒天那から大船二十四艘で押しわたった。
えー・・・陸からではなく海からでも包囲網・・・って当たり前か。
本部半島に今帰仁城跡あるから、海から補給してたらいつまでたっても勝てなくなるな。
今帰仁城の主は、Prince of Nakijinと呼ばれており、王太子の意味を持つ・・・それは別の国(笑)イギリスですな。
ただ、今帰仁城は山北王が滅んだあとは、尚氏の次男や三男が継ぐことになりました。
守りやすく攻めにくい城を家臣に預けたりしたら、危険ですので。
余談になりました。
さて、今日はこのあたりで失礼します。
戦いの続きを書こうとも思いましたが、すごい長くなりそうなので。
朝のコーヒータイム、ではです。
( ^^) _U~~
時刻は夜半三時半ですが、ブログを書きたいと思います。
そして、いきなりですが中山世鑑からの抜粋。
「今の人々の多くは心変わりして、我が方は小勢となったが、多勢を恐れて一戦もせずに降参するのは如何にも口惜しいことだ。そして、山北国をうち建てた祖先に恥をさらすことになる。さあ、中山の軍は攻め寄せてくるがよい。これを一蹴して手柄を見せようではないか。攻め寄せる中山軍が例え数万騎あろうと、これを打ち破るのは造作もないことだ。もし命運尽きて、この戦に敗れるようなことが有れば、その時は潔く自害して、名を後世に残そうぞ。さあ者共、支度をせよ。怖気づいて笑いものになるな」
・・・沖縄にも項羽がいた・・・
いや、ちょいまて。いくらなんでも、この気負いは半端なさすぎでしょ。なんだ、このラスボス感。
ちなみに、項羽は漢楚争覇時代の楚の英雄でして、あまりにも強すぎて誰も勝てなかったんですよ。ですが、軍師張良が包囲網を作って、さらに偽りの講和を持ちかけて受けさせて、その講和を破って攻めるということで、ようやく倒せたという、ものすごいチートな英雄でした。
尚巴志にも、もうこの時期には護佐丸とかも臣下にいますけどね。
でも、ものすごく芯がしっかりした気構え。手ごわいですな。
さて、先に進みます。
尚巴志はいくら山北王が勇者でも、そのうち降参するとみていたのですが、羽地按司が飛脚を飛ばして言上。
「山北王は今は小勢ですが、残りとどまった一騎当千のつわものが、なお三百騎あります。これらを率いて謀反を企てて城にたてこもり、近隣の兵を集めて首里にのぼろうと準備をしております。急いで官軍を遣わして討伐しなければ、由々しき事態となるでしょう」
というわけで、中山王は浦添按司、越来按司、読谷山按司を大将とする二千騎を討手として差し向けた。
そして名護にたどり着くと軍を二手に分けました。越来按司と読谷山按司が背後を責める大将として名護按司を道案内に800騎が山路から山北城に向かいます。
さらに浦添按司、国頭按司、羽地按司を正面の大将として2700騎が羽地の寒天那から大船二十四艘で押しわたった。
えー・・・陸からではなく海からでも包囲網・・・って当たり前か。
本部半島に今帰仁城跡あるから、海から補給してたらいつまでたっても勝てなくなるな。
今帰仁城の主は、Prince of Nakijinと呼ばれており、王太子の意味を持つ・・・それは別の国(笑)イギリスですな。
ただ、今帰仁城は山北王が滅んだあとは、尚氏の次男や三男が継ぐことになりました。
守りやすく攻めにくい城を家臣に預けたりしたら、危険ですので。
余談になりました。
さて、今日はこのあたりで失礼します。
戦いの続きを書こうとも思いましたが、すごい長くなりそうなので。
朝のコーヒータイム、ではです。
( ^^) _U~~
2016年07月24日
山南王対中山王/尚巴志の軌跡2
さてと解体屋のおじさんです、こんにちは。
本日はですね。先月に行った尚巴志の後編を書こうと思いますが、その前に・・・
一応指摘しておきましょうね。
ウィキペディアの尚巴志の項目、間違ってます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E5%B7%B4%E5%BF%97%E7%8E%8B
尚巴志が佐敷按司に就任したのは31歳ですし、中山王よりも先に山南王に即位しています。
証拠は、中山世鑑の写真と記録の画像をUPして証拠としたいと思います。



ま、こんな感じです。
正史を書いて、別の説も併記するとかなら構いませんが、正史ガン無視ってどうよ?(^^;;
というわけでございました。
そして、そろそろ本編の話に入りたいと思います。
佐敷按司から山南王に即位した尚巴志ですが、まだ北部を統括する山北王が残っています。
そして中山王武寧も。
殷の湯王のような例えが中山世鑑に書かれてますね。
「民が待ち望むことは、まるで大干ばつの時に恵みの雨を望むようだった。商いに集まることをやめさせることはなく、田畑をたがやすことを」変えることもしなかった。「わが君を待つ、君がおいでになれば蘇る」」
との故事だそうです。中山世鑑より引用。
そして人々は山南王の軍勢にごちそうを持参して心から迎えたので、ついに武寧王を倒して中山王に即位されました。
と、書き進めたところで気づきましたが・・・
山北王と尚巴志の決戦は少し長くなりますね。
山北王は城に三百騎で立てこもってますが一騎当千のつわものぞろい、尚巴志は約3000騎を揃えますが、苦戦します。
城攻めは三倍の兵がいるのと、あと中山世鑑読み進めてたら山北王は気構えだけなら項羽(漢楚争覇時代の英雄)なみです。強さもそのくらいあったら、ものすごい手こずりますね。
OKです。尚巴志対山北王の決戦は、次回のブログにまわしたいと思います。
本日はこれにて終了、お茶にします。
では、おつかれさまです。( ^^) _U~~
本日はですね。先月に行った尚巴志の後編を書こうと思いますが、その前に・・・
一応指摘しておきましょうね。
ウィキペディアの尚巴志の項目、間違ってます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%9A%E5%B7%B4%E5%BF%97%E7%8E%8B
尚巴志が佐敷按司に就任したのは31歳ですし、中山王よりも先に山南王に即位しています。
証拠は、中山世鑑の写真と記録の画像をUPして証拠としたいと思います。



ま、こんな感じです。
正史を書いて、別の説も併記するとかなら構いませんが、正史ガン無視ってどうよ?(^^;;
というわけでございました。
そして、そろそろ本編の話に入りたいと思います。
佐敷按司から山南王に即位した尚巴志ですが、まだ北部を統括する山北王が残っています。
そして中山王武寧も。
殷の湯王のような例えが中山世鑑に書かれてますね。
「民が待ち望むことは、まるで大干ばつの時に恵みの雨を望むようだった。商いに集まることをやめさせることはなく、田畑をたがやすことを」変えることもしなかった。「わが君を待つ、君がおいでになれば蘇る」」
との故事だそうです。中山世鑑より引用。
そして人々は山南王の軍勢にごちそうを持参して心から迎えたので、ついに武寧王を倒して中山王に即位されました。
と、書き進めたところで気づきましたが・・・
山北王と尚巴志の決戦は少し長くなりますね。
山北王は城に三百騎で立てこもってますが一騎当千のつわものぞろい、尚巴志は約3000騎を揃えますが、苦戦します。
城攻めは三倍の兵がいるのと、あと中山世鑑読み進めてたら山北王は気構えだけなら項羽(漢楚争覇時代の英雄)なみです。強さもそのくらいあったら、ものすごい手こずりますね。
OKです。尚巴志対山北王の決戦は、次回のブログにまわしたいと思います。
本日はこれにて終了、お茶にします。
では、おつかれさまです。( ^^) _U~~
Posted by white_yamada at
04:01
│Comments(0)
2016年06月19日
琉球王国統一序章/尚巴志と李世民
さてと解体屋のおじさんです、今晩は。
さて、ブログで今日から尚巴志の序章を書こうと思いますが、その前に、唐の太宗皇帝「李世民」を少し書きたいと思います。
なぜ李世民を書くのかと言いますと、実は尚巴志は隋唐演義を理想化して行動してたのではないか?と思われる節が有るのです。
推敲一。
佐敷按司、尚思紹を「先代」として立てている。
(太宗皇帝李世民も、父親の李淵を初代とした)
推敲二。
政治は「貞観の治」を模倣。
(貞観の治とは、太宗皇帝李世民の安定期の政治を指す。中国史上最大の安定期とされ、(以下ウィキから引用)「この時代を示す言葉として、『資治通鑑』に「-海内升平,路不拾遺,外戸不閉,商旅野宿焉。」(天下太平であり、道に置き忘れたものは盗まれない。家の戸は閉ざされること無く、旅の商人は野宿をする(ほど治安が良い))との評がある」)
ただし、尚巴志は長男、李世民は次男。
李世民はそのままだと皇帝に即位できないため、長男を殺害しています。
中国史は良いも悪いも全て書き記すので、皇帝でも後世にこういった残虐な逸話が残るわけです。
ただ、李世民をかばうことを言えば、こうしないと自分が長男から殺される可能性が高いので。
次男にもかかわらず、ばらばらになった中国全土を自分が軍隊率いて統一してまわったわけですから。
実は悪い話を書かないの例に織田信長の話もありまして。
織田信長の弟、織田信行は、実はひょっとしたら長男だったのではないか?と疑ってます。
信長はあまりにも優秀すぎるので惣領制な戦国時代では早くから後継者とされたのでしょうが、優秀すぎて周囲の人間がついていけないんですよ。ついていける人間は、秀吉級の人物か、家康級の人物か・・・どっちもチートすぎですがな(^^;;;
ちなみに柴田勝家はいったんは信行派になったりしてました。柴田勝家クラスですら、こうですからね。
閑話休題、元の話題に戻りますと。
んー・・・尚巴志の李世民模倣説は自分の勝手な説ですので、本気にはしないでくださいませ。
ただ、沖縄にもすでに中国の史記などは流入しております。武寧王と察度王が既に冊封されておりますし、久米三六姓も沖縄に移住しておりますので。
さて、尚巴志の話に入ります。
尚巴志は佐敷按司、尚思紹の長男として生まれました。
尚巴志は31歳で佐敷按司となられました。
ちなみにこの方、背が小さかったそうです。5尺に満たないそうだから151cm未満。確かに小さいですね。
なので人々は佐敷小按司と呼んでおりました。
時の山南王は「他魯毎」。中山世鑑には記述が有りませんが、中山世譜(漢文で書かれた中山世鑑)には記述が有ります。
この山南王はおごり高ぶっており、民の負担も顧みず毎日酒宴を繰り返し、按司たちはどんどん離れていきました。
そのため「何ほどのことがあろうか?」と、名君と名高い佐敷按司、尚巴志ごと滅ぼそうと兵を起こしました。
そのため離反した按司たちも尚巴志のもとに集結、他魯毎を滅ぼします。
そして尚巴志を山南王として推戴いたしました。
このあたりなんですが、小説的な脚色できそうですよね。いろいろと面白いこと書けそうだ。
そして浦添へ進軍し支配下におさめると、・・・ゲームでいうとラスボス扱いで良いですかね?
山北王との戦いの話になるのですが、これは来週にまわします。
あさのコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
さて、ブログで今日から尚巴志の序章を書こうと思いますが、その前に、唐の太宗皇帝「李世民」を少し書きたいと思います。
なぜ李世民を書くのかと言いますと、実は尚巴志は隋唐演義を理想化して行動してたのではないか?と思われる節が有るのです。
推敲一。
佐敷按司、尚思紹を「先代」として立てている。
(太宗皇帝李世民も、父親の李淵を初代とした)
推敲二。
政治は「貞観の治」を模倣。
(貞観の治とは、太宗皇帝李世民の安定期の政治を指す。中国史上最大の安定期とされ、(以下ウィキから引用)「この時代を示す言葉として、『資治通鑑』に「-海内升平,路不拾遺,外戸不閉,商旅野宿焉。」(天下太平であり、道に置き忘れたものは盗まれない。家の戸は閉ざされること無く、旅の商人は野宿をする(ほど治安が良い))との評がある」)
ただし、尚巴志は長男、李世民は次男。
李世民はそのままだと皇帝に即位できないため、長男を殺害しています。
中国史は良いも悪いも全て書き記すので、皇帝でも後世にこういった残虐な逸話が残るわけです。
ただ、李世民をかばうことを言えば、こうしないと自分が長男から殺される可能性が高いので。
次男にもかかわらず、ばらばらになった中国全土を自分が軍隊率いて統一してまわったわけですから。
実は悪い話を書かないの例に織田信長の話もありまして。
織田信長の弟、織田信行は、実はひょっとしたら長男だったのではないか?と疑ってます。
信長はあまりにも優秀すぎるので惣領制な戦国時代では早くから後継者とされたのでしょうが、優秀すぎて周囲の人間がついていけないんですよ。ついていける人間は、秀吉級の人物か、家康級の人物か・・・どっちもチートすぎですがな(^^;;;
ちなみに柴田勝家はいったんは信行派になったりしてました。柴田勝家クラスですら、こうですからね。
閑話休題、元の話題に戻りますと。
んー・・・尚巴志の李世民模倣説は自分の勝手な説ですので、本気にはしないでくださいませ。
ただ、沖縄にもすでに中国の史記などは流入しております。武寧王と察度王が既に冊封されておりますし、久米三六姓も沖縄に移住しておりますので。
さて、尚巴志の話に入ります。
尚巴志は佐敷按司、尚思紹の長男として生まれました。
尚巴志は31歳で佐敷按司となられました。
ちなみにこの方、背が小さかったそうです。5尺に満たないそうだから151cm未満。確かに小さいですね。
なので人々は佐敷小按司と呼んでおりました。
時の山南王は「他魯毎」。中山世鑑には記述が有りませんが、中山世譜(漢文で書かれた中山世鑑)には記述が有ります。
この山南王はおごり高ぶっており、民の負担も顧みず毎日酒宴を繰り返し、按司たちはどんどん離れていきました。
そのため「何ほどのことがあろうか?」と、名君と名高い佐敷按司、尚巴志ごと滅ぼそうと兵を起こしました。
そのため離反した按司たちも尚巴志のもとに集結、他魯毎を滅ぼします。
そして尚巴志を山南王として推戴いたしました。
このあたりなんですが、小説的な脚色できそうですよね。いろいろと面白いこと書けそうだ。
そして浦添へ進軍し支配下におさめると、・・・ゲームでいうとラスボス扱いで良いですかね?
山北王との戦いの話になるのですが、これは来週にまわします。
あさのコーヒータイム、お疲れ様です。
( ^^) _U~~
Posted by white_yamada at
04:46
│Comments(0)