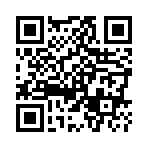2018年02月28日
尚寧王ゆかりの地を探索/てだこウォーク
先日の話ですが、てだこウォークに参加してきました。
てだことは「太陽の子」という意味で、沖縄県浦添市の仮称です。英祖王の墓が浦添にあり、英祖王の父は太陽だったからとか。中山世鑑だと英祖王は按司だけど国王の血筋だから、なんですけどね。
本日なんですが、いつも使っているノートPCは開かずにiPadで書きます。不慣れな点は、ご容赦くださいませ。
さて、先日の話ですが、てだこウォークに参加してきました。2018年2月4日にですね。沖縄にしては寒い10度くらいの気温でした。浦添市運動公園からスタート、歩いて安波茶橋にまで向かいました。安波茶橋は尚寧王が作りました。1597年にとのことです。その6年後に家康は幕府を開きます。
そして江戸幕府開設から更に6年後の1609年徳川秀忠の時代、薩摩は琉球王国に侵攻します。琉球侵攻ですね。
その時には安波茶橋でも戦いがあり、血が流れたという伝説があります。橋の下流には国王に水を献上した「赤皿ガー」というのが有りますが、血が流れたから「赤」という伝説もあり。





赤皿ガーは撮影できませんでした。
このようなかんじで安波茶橋をめぐり、今度は「経塚」という地名に向かいます。
その経塚なんですが高野山の日秀というお坊さんが、妖怪がいたところに、ありがたい経を生めた土地なので「経塚」という地名になったとか。ウィキペディアにも有りました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%A7%80_(%E7%9C%9F%E8%A8%80%E5%AE%97)
写真は撮る余裕がありませんでした(汗)
ちょいと補足すると、
高野山の日秀さんに限らずに、古代日本では南のはてに楽園があると信じられており、終身の意味もこめて船出する人は多かったのです。限られた食料でカヌーみたいな船で旅立つわけです。楽園へと向かうために。たまに沖縄にたどり着く人も居るという。
さて、話を戻しますと、このような感じで回っていき、自分の職場の周りも通って、浦添運動公園に戻りました。
本日のブログは以上になります。
何か面白いネタが浮かびそうで浮かばない、もどかしい感じのブログになりました(汗)
てだことは「太陽の子」という意味で、沖縄県浦添市の仮称です。英祖王の墓が浦添にあり、英祖王の父は太陽だったからとか。中山世鑑だと英祖王は按司だけど国王の血筋だから、なんですけどね。
本日なんですが、いつも使っているノートPCは開かずにiPadで書きます。不慣れな点は、ご容赦くださいませ。
さて、先日の話ですが、てだこウォークに参加してきました。2018年2月4日にですね。沖縄にしては寒い10度くらいの気温でした。浦添市運動公園からスタート、歩いて安波茶橋にまで向かいました。安波茶橋は尚寧王が作りました。1597年にとのことです。その6年後に家康は幕府を開きます。
そして江戸幕府開設から更に6年後の1609年徳川秀忠の時代、薩摩は琉球王国に侵攻します。琉球侵攻ですね。
その時には安波茶橋でも戦いがあり、血が流れたという伝説があります。橋の下流には国王に水を献上した「赤皿ガー」というのが有りますが、血が流れたから「赤」という伝説もあり。
赤皿ガーは撮影できませんでした。
このようなかんじで安波茶橋をめぐり、今度は「経塚」という地名に向かいます。
その経塚なんですが高野山の日秀というお坊さんが、妖怪がいたところに、ありがたい経を生めた土地なので「経塚」という地名になったとか。ウィキペディアにも有りました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%A7%80_(%E7%9C%9F%E8%A8%80%E5%AE%97)
写真は撮る余裕がありませんでした(汗)
ちょいと補足すると、
高野山の日秀さんに限らずに、古代日本では南のはてに楽園があると信じられており、終身の意味もこめて船出する人は多かったのです。限られた食料でカヌーみたいな船で旅立つわけです。楽園へと向かうために。たまに沖縄にたどり着く人も居るという。
さて、話を戻しますと、このような感じで回っていき、自分の職場の周りも通って、浦添運動公園に戻りました。
本日のブログは以上になります。
何か面白いネタが浮かびそうで浮かばない、もどかしい感じのブログになりました(汗)
Posted by white_yamada at 17:15│Comments(0)
│歴史