 › Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 信長の先駆者。独裁者/足利義教編
› Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 信長の先駆者。独裁者/足利義教編2014年11月23日
信長の先駆者。独裁者/足利義教編
さてと解体屋のおじさんです。こんにちは。
そして今日はですが、足利義教について語りたいと思います。
さて、この方なんですが、以前自分は「足利将軍は有力守護大名の議長ていど」と書きました。
この方も本来はそうなるはずだったのです。
この方の前の将軍は兄の義量だったのですが、将軍とは名ばかりで父の義持が握っておりました。
ですが義量は早くして早逝し、父は危篤の状態でも後継者を指名しないために、群臣(三宝院満済や管領・畠山満家)たちが会議を行い、中世では珍しいことに、「くじ引き」で将軍を選ぶことになりました。
くじ引きって、古代では神の意志を問うための宗教儀式だったんですよ。それを中世で行ったので・・・
足利義教の立ち位置は大分変ることになります。つまり、「神の意志で選ばれた将軍」という位置に立ったわけです。
それでも足利義政みたいに何もしなければ、その位置は徐々に後退していきますが、足利義教は将軍という地位を利用して積極的な活動を開始します。
次の記事はwikiからの抜粋。
「まず、三宝院満済を政治顧問に儀礼の形式や訴訟手続きなどを義満時代のものを復活させ、参加者の身分・家柄が固定化された評定衆・引付に代わって、自らが主宰して参加者を指名する御前沙汰を協議機関とすること、管領を経由して行ってきた諸大名への諮問を将軍が直接諮問する[註 5]など、管領の権限抑制策を打ち出した。また、管領を所務沙汰の場から排除する一方で、増加する軍事指揮行動に対処するために、軍勢催促や戦功褒賞においてはこれまでの御内書と並行して管領奉書を用いるようになった」
積極的な組織改革と行動。並の将軍では出来ないでしょ?
この方は還俗して将軍になる前は僧侶でしたが、その僧侶時代も「天台開闢以来の逸材」とか呼ばれておりました。
更に軍事方面もwikiから抜粋。
「軍事力についても、将軍直轄の奉公衆の整備など軍制改革を行って力を得る。そして鎌倉公方足利持氏が、正長から永享に改元したにも拘らず正長の年号を使い続け、また鎌倉五山の住職を勝手に決定するなどの専横を口実とし討伐を試みる。これは関東管領上杉氏の反対に遭い断念するが、代わりに大内盛見に九州征伐を命じた。盛見は戦死したが跡を継いだ甥の大内持世が山名氏の手を借りて渋川氏や少弐氏・大友氏を撃破、腹心となった持世を九州探題とし九州を支配下に置いた。」
つまり、領土拡大に成功している。実は江戸時代の徳川家康も、九州を直接支配下には置けなかったんですよ。
在地の大名が当然いまして、その中には島津がいる。
島津を倒そうと意地を張ることも当然できましたが、天下が傾く可能性が有ったのですね。島津は抵抗の意思を当然見せますし、一歩間違うと内乱になりますから。徳川家といえども足利家よりは権威も権力も有りますが、外様大名とは妥協した政権なのです。外様大名に一定の支配権は認めて、その上に将軍として立っている、くらいの実力者。当然中央集権国家ではない。日本が中央集権国家(近代国家)に突入するには明治維新まで待たなくてはなりません。
話しがそれました。元の話しに戻しますと、日本の中世ではあらゆる勢力が武器を持っております。そのなかで仏教徒でありながら武器を持ち、京都で治外法権を獲得してやりたい放題している勢力、比叡山延暦寺対策に足利義教は取り組み始めます。
比叡山延暦寺と言えば、有名なのが信長の焼き討ちですが・・・実は朝廷が治安維持も放棄して警察(検非違使)が有名無実化しているので、僧侶まで武器持ってやりたい放題の勢力になってたのです。そのなかでも京都で一番勢力が有ったのが比叡山延暦寺。
信長は武装放棄させるために焼き討ちをやらざるを得なかったのです。
ちなみに、その次の時代の秀吉は簡単でした。秀吉の時は高野山も武装していましたが、高野山に「焼き討ちやるぞ」と秀吉が嚇したら屈服したわけです。汚れ役を信長が引き受けてくれたので、対策が楽であったという事です。
宗教というのは難しいものでして、今でも中東では宗教で戦争を行っております。日本でもそういう時代が有ったわけです。
だから誰かが焼き討ちしてでも武装解除させないといけない。
日本には信長,秀吉,家康がいたので、現代の日本は国民の大半が無宗教ですとか述べて平和でいるわけです。
さてと、また話題がそれました。元に戻しますと、やりたい放題の延暦寺対策に、信長よりも先に足利義教は手を付けていた訳です。
だから信長の先駆者と呼んでおります。自分は足利義教のことを。
さらにwikiより抜粋。
「もともと天台座主であった義教は還俗後すぐに弟の義承を天台座主に任じ、天台勢力の取り込みを図った。永享5年(1433年)に延暦寺山徒は幕府の山門奉行飯尾為種や、光聚院猷秀[註 7]らに不正があったとして十二か条からなる弾劾訴訟を行った。満済や管領細川持之が融和策を唱えたため、義教は為種や猷秀を配流することで事件を収めた。しかし山徒は勝訴の勢いにのり、訴訟に同調しなかった園城寺を焼き討ちする事件が起こる。義教は激怒し、自ら兵を率いて園城寺の僧兵とともに比叡山を包囲した。これをみて比叡山側は降伏し、一旦和睦が成立した。
しかし翌年(1434年)7月、延暦寺が鎌倉公方足利持氏と通謀し、義教を呪詛しているとの噂が流れた。義教はただちに近江の守護である京極持高・六角満綱に命じ、比叡山一帯を包囲して物資の流入を妨げた。さらに11月には軍兵が比叡山の門前町である坂本の民家に火をかけ、住民が山上へ避難する騒ぎとなった。延暦寺側が降伏を申し入れ、管領細川持之ら幕府宿老も赦免要請を行ったが、義教はなかなか承諾しなかった。12月10日、持之ら幕府宿老5名が「比叡山赦免が成されなければ、自邸を焼いて本国に退去する」と強硬な要請を再三行った。12日、義教はようやく折れて和睦が成立し、延暦寺代表の山門使節4人を謁見した後に軍を引いた。
しかし義教は本心では許しておらず、同7年(1435年)2月、先の4人を京に招いた。彼らは義教を疑ってなかなか上洛しなかった。しかし、管領の誓紙が差し出されたために4人が出頭したところ、彼らは捕らえられて首をはねられた。これを聞いた延暦寺の山徒は激昂し、抗議のため根本中堂に火をかけ、24人の山徒が焼身自殺した。
炎は京都からも見え、世情は騒然となった。義教は比叡山について噂する者を斬罪に処す触れを出した。その後、山門使節の後任には親幕派の僧侶が新たに任命され、半年後には根本中堂の再建が開始された。」
延暦寺との抗争ですね。更に関東まで平定します。
「永享の乱
鎌倉公方の足利持氏は自分が僧籍に入っていないことから、義持没後には将軍に就任できると信じており、義教を「還俗将軍」と呼び恨んでいた。先の年号問題は持氏の妥協で決着が付いたものの、比叡山の呪詛問題、それに永享10年(1438年)には嫡子足利義久の元服の際に義教を無視し勝手に名前をつけた(当時は慣例として将軍から一字(諱の2文字目、通字の「義」でない方)を拝領していた)ことなどから幕府との関係は一触即発となっていた。そんな時にたびたび持氏を諌めていた関東管領上杉憲実が疎まれたことにより身の危険を感じて領国の上野に逃亡し、持氏の討伐を受けるに至る。義教は好機と見て憲実と結び、関東の諸大名に持氏包囲網を結成させ、持氏討伐の勅令を奉じて朝敵に認定し、同11年(1439年)に関東討伐に至った(永享の乱)。持氏は大敗して剃髪、恭順の姿勢を示した。しかし義教は憲実の助命嘆願にも拘らず持氏一族を殺害した。その後は関東に自己の勢力を広げていくために実子を新しい鎌倉公方として下向させようとしたが、これは上杉氏の反対にあって頓挫している。なお、8代将軍義政(義教の三男)の代になって政知(義教の次男)が幕府公認の鎌倉公方として関東に送り込まれ、義教の計画が実行に移されたかたちになったが、結局政知は鎌倉入りを果たせぬまま伊豆堀越にとどまり、堀越公方と称されることとなった。
関東平定と中央集権の実現
鎌倉を平定した義教であったが、永享12年(1440年)に逃亡していた持氏の遺児の安王丸・春王丸兄弟が結城氏朝に担がれて叛乱を起こした(結城合戦)。義教は隠居していた憲実に討伐を命ずるも、関東諸将の頑強な反抗に遭い、力攻めから兵糧攻めに切り替え、翌年の嘉吉元年(1441年)4月には鎮圧された。春王・安王は京への護送途中で斬られた。また大和永享の乱で越智氏・箸尾氏といった有力国人ともども後南朝勢力を討伐した。これらの乱の鎮定の際には「治罰綸旨」を受けて相手を「朝敵」にする事を行っており、これが戦国期における朝廷の権威復興の一因となったとする説もある[11]。
嘉吉元年(1441年)には、京都・大覚寺を逐電して日向国に潜伏していた弟の義昭を、島津忠国に命じて討たせた。また義教は、斯波氏、畠山氏、山名氏、京極氏、富樫氏、今川氏など有力守護大名に対して、その家督継承に積極的に干渉することにより、将軍の支配力を強める政策を行った。また、意に反した守護大名、一色義貫と土岐持頼は誅殺された。
義教の時代には正長の土一揆や後南朝勢力の反乱など、室町幕府を巡る政治・社会情勢が不穏であり、義教は幕府権力の強化に一定の成果をあげた。」
つまり、直接統治する「絶対領土」の拡大に成功しているわけです。信長も最初は尾張からスタートで、次に岐阜、京都、堺、とどんどん拡大していきましたよね。将軍という地位が有ったとはいえ、信長よりも先に領土拡大に成功しているわけです。並の男では出来ない。
wikiより抜粋。
「6月24日、満祐の子の教康は、結城合戦の祝勝の宴として松囃子(赤松囃子・赤松氏伝統の演能)を献上したいと称して西洞院二条にある邸へ義教を招いた。『嘉吉記』などによると、「鴨の子が沢山できたので、泳ぐさまを御覧下さい」[1]と招いたという。
この宴に相伴した大名は管領細川持之、畠山持永、山名持豊、一色教親、細川持常、大内持世、京極高数、山名熙貴、細川持春、赤松貞村で、義教の介入によって家督を相続した者たちであった。他に公家の正親町三条実雅(正親町三条公治の父、義教の正室正親町三条尹子の兄)らも随行している。
一同が猿楽を観賞していた時、にわかに馬が放たれ、屋敷の門がいっせいに閉じられる大きな物音がたった。癇性な義教は「何事であるか」と叫ぶが、傍らに座していた正親町三条実雅は「雷鳴でありましょう」と呑気に答えた。その直後、障子が開け放たれるや甲冑を着た武者たちが宴の座敷に乱入、赤松氏随一の剛の者安積行秀が播磨国の千種鉄で鍛えた業物を抜くや義教の首をはねてしまった。」
ちょいと詰めが甘かった。いろんな人から憎まれている立場でもありましたので、慎重にいけば良かったのですが。
ただ、義教が存在したことにより、のちの信長も延暦寺対策はやりやすくはなったわけです。
最初に手を付ける人がいかに大変か、ということを物語る話でした。
さてと、足利義教編はここまでにして、朝のコーヒータイムにします。お疲れ様です。
( ^^) _U~~
そして今日はですが、足利義教について語りたいと思います。
さて、この方なんですが、以前自分は「足利将軍は有力守護大名の議長ていど」と書きました。
この方も本来はそうなるはずだったのです。
この方の前の将軍は兄の義量だったのですが、将軍とは名ばかりで父の義持が握っておりました。
ですが義量は早くして早逝し、父は危篤の状態でも後継者を指名しないために、群臣(三宝院満済や管領・畠山満家)たちが会議を行い、中世では珍しいことに、「くじ引き」で将軍を選ぶことになりました。
くじ引きって、古代では神の意志を問うための宗教儀式だったんですよ。それを中世で行ったので・・・
足利義教の立ち位置は大分変ることになります。つまり、「神の意志で選ばれた将軍」という位置に立ったわけです。
それでも足利義政みたいに何もしなければ、その位置は徐々に後退していきますが、足利義教は将軍という地位を利用して積極的な活動を開始します。
次の記事はwikiからの抜粋。
「まず、三宝院満済を政治顧問に儀礼の形式や訴訟手続きなどを義満時代のものを復活させ、参加者の身分・家柄が固定化された評定衆・引付に代わって、自らが主宰して参加者を指名する御前沙汰を協議機関とすること、管領を経由して行ってきた諸大名への諮問を将軍が直接諮問する[註 5]など、管領の権限抑制策を打ち出した。また、管領を所務沙汰の場から排除する一方で、増加する軍事指揮行動に対処するために、軍勢催促や戦功褒賞においてはこれまでの御内書と並行して管領奉書を用いるようになった」
積極的な組織改革と行動。並の将軍では出来ないでしょ?
この方は還俗して将軍になる前は僧侶でしたが、その僧侶時代も「天台開闢以来の逸材」とか呼ばれておりました。
更に軍事方面もwikiから抜粋。
「軍事力についても、将軍直轄の奉公衆の整備など軍制改革を行って力を得る。そして鎌倉公方足利持氏が、正長から永享に改元したにも拘らず正長の年号を使い続け、また鎌倉五山の住職を勝手に決定するなどの専横を口実とし討伐を試みる。これは関東管領上杉氏の反対に遭い断念するが、代わりに大内盛見に九州征伐を命じた。盛見は戦死したが跡を継いだ甥の大内持世が山名氏の手を借りて渋川氏や少弐氏・大友氏を撃破、腹心となった持世を九州探題とし九州を支配下に置いた。」
つまり、領土拡大に成功している。実は江戸時代の徳川家康も、九州を直接支配下には置けなかったんですよ。
在地の大名が当然いまして、その中には島津がいる。
島津を倒そうと意地を張ることも当然できましたが、天下が傾く可能性が有ったのですね。島津は抵抗の意思を当然見せますし、一歩間違うと内乱になりますから。徳川家といえども足利家よりは権威も権力も有りますが、外様大名とは妥協した政権なのです。外様大名に一定の支配権は認めて、その上に将軍として立っている、くらいの実力者。当然中央集権国家ではない。日本が中央集権国家(近代国家)に突入するには明治維新まで待たなくてはなりません。
話しがそれました。元の話しに戻しますと、日本の中世ではあらゆる勢力が武器を持っております。そのなかで仏教徒でありながら武器を持ち、京都で治外法権を獲得してやりたい放題している勢力、比叡山延暦寺対策に足利義教は取り組み始めます。
比叡山延暦寺と言えば、有名なのが信長の焼き討ちですが・・・実は朝廷が治安維持も放棄して警察(検非違使)が有名無実化しているので、僧侶まで武器持ってやりたい放題の勢力になってたのです。そのなかでも京都で一番勢力が有ったのが比叡山延暦寺。
信長は武装放棄させるために焼き討ちをやらざるを得なかったのです。
ちなみに、その次の時代の秀吉は簡単でした。秀吉の時は高野山も武装していましたが、高野山に「焼き討ちやるぞ」と秀吉が嚇したら屈服したわけです。汚れ役を信長が引き受けてくれたので、対策が楽であったという事です。
宗教というのは難しいものでして、今でも中東では宗教で戦争を行っております。日本でもそういう時代が有ったわけです。
だから誰かが焼き討ちしてでも武装解除させないといけない。
日本には信長,秀吉,家康がいたので、現代の日本は国民の大半が無宗教ですとか述べて平和でいるわけです。
さてと、また話題がそれました。元に戻しますと、やりたい放題の延暦寺対策に、信長よりも先に足利義教は手を付けていた訳です。
だから信長の先駆者と呼んでおります。自分は足利義教のことを。
さらにwikiより抜粋。
「もともと天台座主であった義教は還俗後すぐに弟の義承を天台座主に任じ、天台勢力の取り込みを図った。永享5年(1433年)に延暦寺山徒は幕府の山門奉行飯尾為種や、光聚院猷秀[註 7]らに不正があったとして十二か条からなる弾劾訴訟を行った。満済や管領細川持之が融和策を唱えたため、義教は為種や猷秀を配流することで事件を収めた。しかし山徒は勝訴の勢いにのり、訴訟に同調しなかった園城寺を焼き討ちする事件が起こる。義教は激怒し、自ら兵を率いて園城寺の僧兵とともに比叡山を包囲した。これをみて比叡山側は降伏し、一旦和睦が成立した。
しかし翌年(1434年)7月、延暦寺が鎌倉公方足利持氏と通謀し、義教を呪詛しているとの噂が流れた。義教はただちに近江の守護である京極持高・六角満綱に命じ、比叡山一帯を包囲して物資の流入を妨げた。さらに11月には軍兵が比叡山の門前町である坂本の民家に火をかけ、住民が山上へ避難する騒ぎとなった。延暦寺側が降伏を申し入れ、管領細川持之ら幕府宿老も赦免要請を行ったが、義教はなかなか承諾しなかった。12月10日、持之ら幕府宿老5名が「比叡山赦免が成されなければ、自邸を焼いて本国に退去する」と強硬な要請を再三行った。12日、義教はようやく折れて和睦が成立し、延暦寺代表の山門使節4人を謁見した後に軍を引いた。
しかし義教は本心では許しておらず、同7年(1435年)2月、先の4人を京に招いた。彼らは義教を疑ってなかなか上洛しなかった。しかし、管領の誓紙が差し出されたために4人が出頭したところ、彼らは捕らえられて首をはねられた。これを聞いた延暦寺の山徒は激昂し、抗議のため根本中堂に火をかけ、24人の山徒が焼身自殺した。
炎は京都からも見え、世情は騒然となった。義教は比叡山について噂する者を斬罪に処す触れを出した。その後、山門使節の後任には親幕派の僧侶が新たに任命され、半年後には根本中堂の再建が開始された。」
延暦寺との抗争ですね。更に関東まで平定します。
「永享の乱
鎌倉公方の足利持氏は自分が僧籍に入っていないことから、義持没後には将軍に就任できると信じており、義教を「還俗将軍」と呼び恨んでいた。先の年号問題は持氏の妥協で決着が付いたものの、比叡山の呪詛問題、それに永享10年(1438年)には嫡子足利義久の元服の際に義教を無視し勝手に名前をつけた(当時は慣例として将軍から一字(諱の2文字目、通字の「義」でない方)を拝領していた)ことなどから幕府との関係は一触即発となっていた。そんな時にたびたび持氏を諌めていた関東管領上杉憲実が疎まれたことにより身の危険を感じて領国の上野に逃亡し、持氏の討伐を受けるに至る。義教は好機と見て憲実と結び、関東の諸大名に持氏包囲網を結成させ、持氏討伐の勅令を奉じて朝敵に認定し、同11年(1439年)に関東討伐に至った(永享の乱)。持氏は大敗して剃髪、恭順の姿勢を示した。しかし義教は憲実の助命嘆願にも拘らず持氏一族を殺害した。その後は関東に自己の勢力を広げていくために実子を新しい鎌倉公方として下向させようとしたが、これは上杉氏の反対にあって頓挫している。なお、8代将軍義政(義教の三男)の代になって政知(義教の次男)が幕府公認の鎌倉公方として関東に送り込まれ、義教の計画が実行に移されたかたちになったが、結局政知は鎌倉入りを果たせぬまま伊豆堀越にとどまり、堀越公方と称されることとなった。
関東平定と中央集権の実現
鎌倉を平定した義教であったが、永享12年(1440年)に逃亡していた持氏の遺児の安王丸・春王丸兄弟が結城氏朝に担がれて叛乱を起こした(結城合戦)。義教は隠居していた憲実に討伐を命ずるも、関東諸将の頑強な反抗に遭い、力攻めから兵糧攻めに切り替え、翌年の嘉吉元年(1441年)4月には鎮圧された。春王・安王は京への護送途中で斬られた。また大和永享の乱で越智氏・箸尾氏といった有力国人ともども後南朝勢力を討伐した。これらの乱の鎮定の際には「治罰綸旨」を受けて相手を「朝敵」にする事を行っており、これが戦国期における朝廷の権威復興の一因となったとする説もある[11]。
嘉吉元年(1441年)には、京都・大覚寺を逐電して日向国に潜伏していた弟の義昭を、島津忠国に命じて討たせた。また義教は、斯波氏、畠山氏、山名氏、京極氏、富樫氏、今川氏など有力守護大名に対して、その家督継承に積極的に干渉することにより、将軍の支配力を強める政策を行った。また、意に反した守護大名、一色義貫と土岐持頼は誅殺された。
義教の時代には正長の土一揆や後南朝勢力の反乱など、室町幕府を巡る政治・社会情勢が不穏であり、義教は幕府権力の強化に一定の成果をあげた。」
つまり、直接統治する「絶対領土」の拡大に成功しているわけです。信長も最初は尾張からスタートで、次に岐阜、京都、堺、とどんどん拡大していきましたよね。将軍という地位が有ったとはいえ、信長よりも先に領土拡大に成功しているわけです。並の男では出来ない。
wikiより抜粋。
「6月24日、満祐の子の教康は、結城合戦の祝勝の宴として松囃子(赤松囃子・赤松氏伝統の演能)を献上したいと称して西洞院二条にある邸へ義教を招いた。『嘉吉記』などによると、「鴨の子が沢山できたので、泳ぐさまを御覧下さい」[1]と招いたという。
この宴に相伴した大名は管領細川持之、畠山持永、山名持豊、一色教親、細川持常、大内持世、京極高数、山名熙貴、細川持春、赤松貞村で、義教の介入によって家督を相続した者たちであった。他に公家の正親町三条実雅(正親町三条公治の父、義教の正室正親町三条尹子の兄)らも随行している。
一同が猿楽を観賞していた時、にわかに馬が放たれ、屋敷の門がいっせいに閉じられる大きな物音がたった。癇性な義教は「何事であるか」と叫ぶが、傍らに座していた正親町三条実雅は「雷鳴でありましょう」と呑気に答えた。その直後、障子が開け放たれるや甲冑を着た武者たちが宴の座敷に乱入、赤松氏随一の剛の者安積行秀が播磨国の千種鉄で鍛えた業物を抜くや義教の首をはねてしまった。」
ちょいと詰めが甘かった。いろんな人から憎まれている立場でもありましたので、慎重にいけば良かったのですが。
ただ、義教が存在したことにより、のちの信長も延暦寺対策はやりやすくはなったわけです。
最初に手を付ける人がいかに大変か、ということを物語る話でした。
さてと、足利義教編はここまでにして、朝のコーヒータイムにします。お疲れ様です。
( ^^) _U~~
PS:
自分の日本史ブログは井沢元彦氏の「逆説の日本史」シリーズの影響を受けて書いております。
よろしかったら、本元もお読みくださいませ。
https://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E4%BA%95%E6%B2%A2+%E5%85%83%E5%BD%A6%E9%80%86%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2&tag=googhydr-22&index=stripbooks&jp-ad-ap=0&hvadid=82218512087&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14601887069301334565&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009802&hvtargid=kwd-7469179427&ref=pd_sl_npsr3bjnm_e
自分の日本史ブログは井沢元彦氏の「逆説の日本史」シリーズの影響を受けて書いております。
よろしかったら、本元もお読みくださいませ。
https://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E4%BA%95%E6%B2%A2+%E5%85%83%E5%BD%A6%E9%80%86%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2&tag=googhydr-22&index=stripbooks&jp-ad-ap=0&hvadid=82218512087&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14601887069301334565&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009802&hvtargid=kwd-7469179427&ref=pd_sl_npsr3bjnm_e
Posted by white_yamada at 06:15│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|


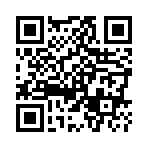
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。