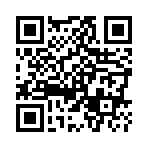› Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 日本の土地問題(歴史)元寇から建武の新政へ|後醍醐天皇編
› Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 日本の土地問題(歴史)元寇から建武の新政へ|後醍醐天皇編2014年10月11日
日本の土地問題(歴史)元寇から建武の新政へ|後醍醐天皇編
さてと、本日は沖縄県は台風なのでブログ書いておきたいと思います。
こんにちは、解体屋のおじさんです。
先週述べたとおり元寇でダメージを受けた幕府は均分相続制の行きづまりも有り、報酬を与えることが出来ずに不満が高まったところで・・・
・・・この天皇は本当に行動的で、天皇というより皇帝に見えるなあ・・・後醍醐天皇が歴史の表舞台に立つわけですが。
まず先に後嵯峨天皇の行為について先に述べようかな?
後醍醐天皇の曾祖父の後嵯峨天皇なんですが、子供は三名ほど兄弟がおりまして。
でも天皇の椅子は一つしかないので、交互に二人の兄弟には天皇の位を譲ったわけです。
子供たち兄弟にも更に子供たち(兄弟/孫)ができると、そんな先例が有るもんだから更に兄弟に交互に天皇位を与えてしまいますよね。
そんなかんじで天皇位がたらいまわしになっていっている状況の中で、後醍醐天皇は二つに分かれた血筋の天皇家、持明院統と大覚寺統の大覚寺統の更に次男という形で生まれてきたわけです。
いちおう何とか天皇にはなれたけど、早く辞めろとせっつかれるし、自分の子供は立太子できないしということで・・・
朝廷に色々と関与する幕府を密かに討幕を図るようになるわけです。
元寇の後になりますが・・・wikiより抜粋。
「元弘元年(1331年)、再度の倒幕計画が側近吉田定房の密告により発覚し身辺に危険が迫ったため急遽京都脱出を決断、三種の神器を持って挙兵した。はじめ比叡山に拠ろうとして失敗し、笠置山(現京都府相楽郡笠置町内)に籠城するが、圧倒的な兵力を擁した幕府軍の前に落城して捕らえられる。これを元弘の乱(元弘の変)と呼ぶ。」
というわけで、倒幕も最初は失敗しているわけです。普通の人ならここで諦めますよね・・・廃位にまでされてしまったし・・・
でも、Emperor Godaigoは全く諦めてないわけです(^^;;
流刑先の隠岐島から脱出した後醍醐天皇は伯耆船上山(現鳥取県東伯郡琴浦町内)で挙兵します。二度目の倒幕活動を開始。
ただ、今回は悪党と呼ばれる赤松円心や楠正成があちらこちらで倒幕の火を放っていたので、象徴が有れば諸勢力を統合できるということもあり、さらに鎌倉幕府の最有力御家人「足利高氏(後に尊氏と改名)」も幕府に謀反することにより鎌倉幕府方は総崩れになり、新田義貞は鎌倉を攻撃することで鎌倉幕府は歴史に幕を閉じることになります。
そして建武の新政がスタートするわけですが・・・
ここで、足利高氏と後醍醐天皇の思惑は違っていることが鮮明になるんですよ。
後醍醐天皇は「天皇親政」わかりやすくいうと、天皇が直接政治をしたいんですね。
後醍醐天皇の諡号「後醍醐」は、本人が自ら決めています。
昔、「醍醐天皇」が直接政治を行った時代が有って、その時は平和で豊かだった、という言い伝えがあったわけです。
その言い伝えにあやかったと。
でも足利高氏は幕府システムは上手くいっているから「クーデター」で大丈夫、という考えだったわけです。
そして朝廷には「高氏無し」という言葉が噂として広まっていきます。
有力武士である高氏には何の恩賞も出さない・・・いや、一つだけあります。
高氏に後醍醐天皇みずからの名前である・・・諱になりますが「尊治」の「尊」の字を足利高氏に送ったわけです。
そして改名して「足利尊氏」となった。
こんな例は後にも先にも、この一事だけですので、すごいありがたい話ではあるのですが・・・まあ、でも、名誉ではあるけど実質上の褒美は無しってことでも有ります。
当然幕府側(元農民の武士たち)は不満を高まらせていくわけです。
これもwikiからですが、二条河原で落書きされるわけです。内容は、こう。
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)
生頸 還俗 自由(まま)出家
俄大名 迷者
安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)
本領ハナルヽ訴訟人 文書入タル細葛(ほそつづら)
追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)
器用ノ堪否(かんぷ)沙汰モナク モルル人ナキ決断所
キツケヌ冠上ノキヌ 持モナラハヌ杓持テ 内裏マシワリ珍シヤ
賢者カホナル伝奏ハ 我モ我モトミユレトモ
巧ナリケル詐(いつわり)ハ ヲロカナルニヤヲトルラム
為中美物(いなかびぶつ)[1]ニアキミチテ マナ板烏帽子ユカメツヽ 気色メキタル京侍
タソカレ時ニ成ヌレハ ウカレテアリク色好(いろごのみ) イクソハクソヤ数不知(しれず) 内裏ヲカミト名付タル
人ノ妻鞆(めども)ノウカレメハ ヨソノミル目モ心地アシ
尾羽ヲレユカムエセ小鷹 手コトニ誰モスエタレト 鳥トル事ハ更ニナシ
鉛作ノオホ刀 太刀ヨリオホキニコシラヘテ 前サカリニソ指ホラス
ハサラ扇[2]ノ五骨 ヒロコシヤセ馬薄小袖
日銭ノ質ノ古具足 関東武士ノカコ出仕
下衆上臈ノキハモナク 大口(おおぐち)ニキル美精好(びせいごう)[3]
鎧直垂猶不捨(すてず) 弓モ引ヱヌ犬追物
落馬矢数ニマサリタリ 誰ヲ師匠トナケレトモ
遍(あまねく)ハヤル小笠懸 事新キ風情也
京鎌倉ヲコキマセテ 一座ソロハヌエセ連歌
在々所々ノ歌連歌 点者ニナラヌ人ソナキ
譜第非成ノ差別ナク 自由狼藉ノ世界也
犬田楽ハ関東ノ ホロフル物ト云ナカラ 田楽ハナヲハヤル也
茶香十炷(ちゃこうじっしゅ)[4]ノ寄合モ 鎌倉釣ニ有鹿ト 都ハイトヽ倍増ス
町コトニ立篝屋(かがりや)ハ 荒涼五間板三枚
幕引マワス役所鞆 其数シラス満々リ
諸人ノ敷地不定 半作ノ家是多シ
去年火災ノ空地共 クソ福ニコソナリニケレ
適(たまたま)ノコル家々ハ 点定セラレテ置去ヌ
非職ノ兵仗ハヤリツヽ 路次ノ礼儀辻々ハナシ
花山桃林サヒシクテ 牛馬華洛ニ遍満ス
四夷ヲシツメシ鎌倉ノ 右大将家ノ掟ヨリ 只品有シ武士モミナ ナメンタラニソ今ハナル
朝ニ牛馬ヲ飼ナカラ 夕ニ賞アル功臣ハ 左右ニオヨハヌ事ソカシ
サセル忠功ナケレトモ 過分ノ昇進スルモアリ 定テ損ソアルラント 仰テ信ヲトルハカリ
天下一統メズラシヤ 御代ニ生テサマザマノ 事ヲミキクゾ不思議ナル
京童ノ口ズサミ 十分ノ一ヲモラスナリ
綸旨とは天皇の命令文書なんですが、代理人が書いても良いので、後醍醐天皇は愛用していたのですね。
そして雑所決断所で、自分がとりあげた土地問題なんかも全部決めているわけです。
国衙領も荘園も地頭も守護も存在するのに、幕府の仲介もなく、朝廷の補佐もなく、天皇だけで全部決めようとして、さすがに無理と気づいて雑所決断所というシステムも作った。
でも朝令暮改だから混乱する一方と。
というわけで足利尊氏は離反し鎌倉で勝手に恩賞を与え、後醍醐天皇は討伐に新田義貞を派遣。
一時は負けて足利尊氏は九州に落ち延びますが・・・ここで多分、日本の軍師としてなら一番の策士「楠正成」は和睦を勧めるわけです。
「足利尊氏が九州で兵を蓄えて京都に攻め込んでくる」・・・多分、この人なら読めてたんでしょうね、先行きを。
後醍醐天皇と側近は一笑してお終いとなってしまいますが、楠正成の予言通り足利尊氏は京都に攻め上ってきました。
そして戦い・・・楠は討ち死にしてしまいます。
そして京都に攻め入った足利尊氏は後醍醐天皇を廃位して持明院統の光明天皇をたてるのですが・・・
えー・・・また幽閉されていた花山院から脱出します。後醍醐天皇は・・・何なんだ、この方は(^^;;
そして吉野に逃れて、「渡した三種の神器は偽物だ」と宣言し、
吉野に南朝を設立します。
史上初の朝廷が二つある時代の到来です。よほどの政治家が出ない限り、ずっと争いは続くことになる。
そのあたりを収束させるのは足利幕府三代目将軍の足利義満が登場するまでまたなくてはならないです。
というところで、今日のタイピングは止めておきたいと思います。
コーヒータイム。お疲れ様です。
こんにちは、解体屋のおじさんです。
先週述べたとおり元寇でダメージを受けた幕府は均分相続制の行きづまりも有り、報酬を与えることが出来ずに不満が高まったところで・・・
・・・この天皇は本当に行動的で、天皇というより皇帝に見えるなあ・・・後醍醐天皇が歴史の表舞台に立つわけですが。
まず先に後嵯峨天皇の行為について先に述べようかな?
後醍醐天皇の曾祖父の後嵯峨天皇なんですが、子供は三名ほど兄弟がおりまして。
でも天皇の椅子は一つしかないので、交互に二人の兄弟には天皇の位を譲ったわけです。
子供たち兄弟にも更に子供たち(兄弟/孫)ができると、そんな先例が有るもんだから更に兄弟に交互に天皇位を与えてしまいますよね。
そんなかんじで天皇位がたらいまわしになっていっている状況の中で、後醍醐天皇は二つに分かれた血筋の天皇家、持明院統と大覚寺統の大覚寺統の更に次男という形で生まれてきたわけです。
いちおう何とか天皇にはなれたけど、早く辞めろとせっつかれるし、自分の子供は立太子できないしということで・・・
朝廷に色々と関与する幕府を密かに討幕を図るようになるわけです。
元寇の後になりますが・・・wikiより抜粋。
「元弘元年(1331年)、再度の倒幕計画が側近吉田定房の密告により発覚し身辺に危険が迫ったため急遽京都脱出を決断、三種の神器を持って挙兵した。はじめ比叡山に拠ろうとして失敗し、笠置山(現京都府相楽郡笠置町内)に籠城するが、圧倒的な兵力を擁した幕府軍の前に落城して捕らえられる。これを元弘の乱(元弘の変)と呼ぶ。」
というわけで、倒幕も最初は失敗しているわけです。普通の人ならここで諦めますよね・・・廃位にまでされてしまったし・・・
でも、Emperor Godaigoは全く諦めてないわけです(^^;;
流刑先の隠岐島から脱出した後醍醐天皇は伯耆船上山(現鳥取県東伯郡琴浦町内)で挙兵します。二度目の倒幕活動を開始。
ただ、今回は悪党と呼ばれる赤松円心や楠正成があちらこちらで倒幕の火を放っていたので、象徴が有れば諸勢力を統合できるということもあり、さらに鎌倉幕府の最有力御家人「足利高氏(後に尊氏と改名)」も幕府に謀反することにより鎌倉幕府方は総崩れになり、新田義貞は鎌倉を攻撃することで鎌倉幕府は歴史に幕を閉じることになります。
そして建武の新政がスタートするわけですが・・・
ここで、足利高氏と後醍醐天皇の思惑は違っていることが鮮明になるんですよ。
後醍醐天皇は「天皇親政」わかりやすくいうと、天皇が直接政治をしたいんですね。
後醍醐天皇の諡号「後醍醐」は、本人が自ら決めています。
昔、「醍醐天皇」が直接政治を行った時代が有って、その時は平和で豊かだった、という言い伝えがあったわけです。
その言い伝えにあやかったと。
でも足利高氏は幕府システムは上手くいっているから「クーデター」で大丈夫、という考えだったわけです。
そして朝廷には「高氏無し」という言葉が噂として広まっていきます。
有力武士である高氏には何の恩賞も出さない・・・いや、一つだけあります。
高氏に後醍醐天皇みずからの名前である・・・諱になりますが「尊治」の「尊」の字を足利高氏に送ったわけです。
そして改名して「足利尊氏」となった。
こんな例は後にも先にも、この一事だけですので、すごいありがたい話ではあるのですが・・・まあ、でも、名誉ではあるけど実質上の褒美は無しってことでも有ります。
当然幕府側(元農民の武士たち)は不満を高まらせていくわけです。
これもwikiからですが、二条河原で落書きされるわけです。内容は、こう。
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)
生頸 還俗 自由(まま)出家
俄大名 迷者
安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)
本領ハナルヽ訴訟人 文書入タル細葛(ほそつづら)
追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)
器用ノ堪否(かんぷ)沙汰モナク モルル人ナキ決断所
キツケヌ冠上ノキヌ 持モナラハヌ杓持テ 内裏マシワリ珍シヤ
賢者カホナル伝奏ハ 我モ我モトミユレトモ
巧ナリケル詐(いつわり)ハ ヲロカナルニヤヲトルラム
為中美物(いなかびぶつ)[1]ニアキミチテ マナ板烏帽子ユカメツヽ 気色メキタル京侍
タソカレ時ニ成ヌレハ ウカレテアリク色好(いろごのみ) イクソハクソヤ数不知(しれず) 内裏ヲカミト名付タル
人ノ妻鞆(めども)ノウカレメハ ヨソノミル目モ心地アシ
尾羽ヲレユカムエセ小鷹 手コトニ誰モスエタレト 鳥トル事ハ更ニナシ
鉛作ノオホ刀 太刀ヨリオホキニコシラヘテ 前サカリニソ指ホラス
ハサラ扇[2]ノ五骨 ヒロコシヤセ馬薄小袖
日銭ノ質ノ古具足 関東武士ノカコ出仕
下衆上臈ノキハモナク 大口(おおぐち)ニキル美精好(びせいごう)[3]
鎧直垂猶不捨(すてず) 弓モ引ヱヌ犬追物
落馬矢数ニマサリタリ 誰ヲ師匠トナケレトモ
遍(あまねく)ハヤル小笠懸 事新キ風情也
京鎌倉ヲコキマセテ 一座ソロハヌエセ連歌
在々所々ノ歌連歌 点者ニナラヌ人ソナキ
譜第非成ノ差別ナク 自由狼藉ノ世界也
犬田楽ハ関東ノ ホロフル物ト云ナカラ 田楽ハナヲハヤル也
茶香十炷(ちゃこうじっしゅ)[4]ノ寄合モ 鎌倉釣ニ有鹿ト 都ハイトヽ倍増ス
町コトニ立篝屋(かがりや)ハ 荒涼五間板三枚
幕引マワス役所鞆 其数シラス満々リ
諸人ノ敷地不定 半作ノ家是多シ
去年火災ノ空地共 クソ福ニコソナリニケレ
適(たまたま)ノコル家々ハ 点定セラレテ置去ヌ
非職ノ兵仗ハヤリツヽ 路次ノ礼儀辻々ハナシ
花山桃林サヒシクテ 牛馬華洛ニ遍満ス
四夷ヲシツメシ鎌倉ノ 右大将家ノ掟ヨリ 只品有シ武士モミナ ナメンタラニソ今ハナル
朝ニ牛馬ヲ飼ナカラ 夕ニ賞アル功臣ハ 左右ニオヨハヌ事ソカシ
サセル忠功ナケレトモ 過分ノ昇進スルモアリ 定テ損ソアルラント 仰テ信ヲトルハカリ
天下一統メズラシヤ 御代ニ生テサマザマノ 事ヲミキクゾ不思議ナル
京童ノ口ズサミ 十分ノ一ヲモラスナリ
綸旨とは天皇の命令文書なんですが、代理人が書いても良いので、後醍醐天皇は愛用していたのですね。
そして雑所決断所で、自分がとりあげた土地問題なんかも全部決めているわけです。
国衙領も荘園も地頭も守護も存在するのに、幕府の仲介もなく、朝廷の補佐もなく、天皇だけで全部決めようとして、さすがに無理と気づいて雑所決断所というシステムも作った。
でも朝令暮改だから混乱する一方と。
というわけで足利尊氏は離反し鎌倉で勝手に恩賞を与え、後醍醐天皇は討伐に新田義貞を派遣。
一時は負けて足利尊氏は九州に落ち延びますが・・・ここで多分、日本の軍師としてなら一番の策士「楠正成」は和睦を勧めるわけです。
「足利尊氏が九州で兵を蓄えて京都に攻め込んでくる」・・・多分、この人なら読めてたんでしょうね、先行きを。
後醍醐天皇と側近は一笑してお終いとなってしまいますが、楠正成の予言通り足利尊氏は京都に攻め上ってきました。
そして戦い・・・楠は討ち死にしてしまいます。
そして京都に攻め入った足利尊氏は後醍醐天皇を廃位して持明院統の光明天皇をたてるのですが・・・
えー・・・また幽閉されていた花山院から脱出します。後醍醐天皇は・・・何なんだ、この方は(^^;;
そして吉野に逃れて、「渡した三種の神器は偽物だ」と宣言し、
吉野に南朝を設立します。
史上初の朝廷が二つある時代の到来です。よほどの政治家が出ない限り、ずっと争いは続くことになる。
そのあたりを収束させるのは足利幕府三代目将軍の足利義満が登場するまでまたなくてはならないです。
というところで、今日のタイピングは止めておきたいと思います。
コーヒータイム。お疲れ様です。
PS:
自分の日本史ブログは井沢元彦氏の「逆説の日本史」シリーズの影響を受けて書いております。
よろしかったら、本元もお読みくださいませ。
https://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E4%BA%95%E6%B2%A2+%E5%85%83%E5%BD%A6%E9%80%86%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2&tag=googhydr-22&index=stripbooks&jp-ad-ap=0&hvadid=82218512087&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14601887069301334565&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009802&hvtargid=kwd-7469179427&ref=pd_sl_npsr3bjnm_e
自分の日本史ブログは井沢元彦氏の「逆説の日本史」シリーズの影響を受けて書いております。
よろしかったら、本元もお読みくださいませ。
https://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E4%BA%95%E6%B2%A2+%E5%85%83%E5%BD%A6%E9%80%86%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2&tag=googhydr-22&index=stripbooks&jp-ad-ap=0&hvadid=82218512087&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14601887069301334565&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009802&hvtargid=kwd-7469179427&ref=pd_sl_npsr3bjnm_e
Posted by white_yamada at 04:39│Comments(0)