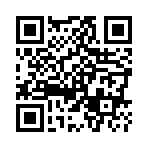› Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 確実に歴史が変わった!!!「本能寺の変」
› Ruby勉強会(Ryukyu Ruby's Rookies)と徒然なる歴史評論 › 確実に歴史が変わった!!!「本能寺の変」2014年09月14日
確実に歴史が変わった!!!「本能寺の変」
さてと、日曜日のブログを書こうと思います。こんにちは。
本日のテーマは・・・このテーマは語りつくされすぎなんだけど、これが有ったのと無かったのとでは確実に歴史が変わっている事件。
「本能寺の変」を語りたいと思います。
この事件の後に天下人になるのが、豊臣秀吉、徳川家康。
上の二人は、金ヶ崎の戦いで「しんがり」を務めるほどのオールラウンドプレイヤー。
でも、信長にとっては部下なんですね。
家康は一応同盟者ではあるんだけど、勢力的には三河周辺の地域が中心の東海部門担当という感じ。
秀吉は信長の部下なんだけど、秀吉級の部下は他にも、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、滝川一益などがいます。
ちなみに信長が部下をほめるとき、一番最初にほめるのが明智光秀。秀吉は三人目くらいなんです。
一番トップは信長で長男に信忠もいる。
えっと、そのまえに何故、秀吉と家康がオールラウンドプレイヤーなのか、というのを説明します。
「しんがり」というのは逃げる時に一番最後で待機して、勢いにのってる敵が来たら追い払って味方を逃す、という戦いです。
もし敵に大将級の首が有ったとしても見逃さなくてはならない。逃げながら戦い、味方を生きのばせることに全力を尽くす。
戦いには、例えば突撃が得意な人、城攻めが得意な人、いろいろいます。でも左記に書いたのは、全部勝っている時にこそ影響力を発揮するものです。
負けている時に突撃が得意でも意味がない、城攻めが得意でも意味がない。敵側がそういった人を差し向けてくる。
そこを守り、追い払い、できるかぎり味方を生きのばらせる。敵が襲ってきたら被害を最小限にとどめる。
防御力と相手を追い払う攻撃力と戦略的な判断が出来る人材がいる、ということになります。
その戦い、信長が負けた金ヶ崎の退き口で、しんがりを務めたのが羽柴秀吉と徳川家康。
名古屋だったかな?この戦いをトップの信長も含めて三英傑のそろい踏みとか呼んでいるそうです。
話しがそれました。元の話題、本能寺の変にもどすと、
もし、光秀が裏切らなかった場合、このメンバーが全員信長の指揮の下で天下統一するわけです。
秀吉は同格の柴田勝家とかを滅ぼしておりますが、その必要もなくなる、と。
信長自身も長篠の戦いで、鉄砲使って武田騎馬隊を撃退とか、効果的な戦略を次々とたてていきますので・・・
他にも政経一体の都市構想(岐阜城)とか、信長はどんどん新しい発想を浮かべ実現していく。
信長が作った城の有名なものに安土城とかありますが、本当は信長は大阪に建てたかったんじゃないかな?
信長が生きていたころは、大阪には石山本願寺がありまして、抗争中でしたので。
秀吉はちゃっかり自分の案として受け継いだ、と。
大阪の利便性も述べておきますと、大阪は平野が二つあって都市が作りやすく、目の前に大阪湾が有るので海上輸送された品物を大阪にすぐに輸送することが可能であり、陸路だと日本の中心にあたり、淀川から真水を確保できて、その川を通って琵琶湖にまで船で水上輸送が出来るという、たぶん信長の構想「政経合体の都市構想」には一番の適地だったかと思います。
でも石山本願寺が抵抗していたので、信長の代では果たせなかった。そこを秀吉が受け継いだ、そういうことになるかと。
うん、さらに話題がそれました。話を元に戻すと、
「明智光秀はなぜ信長を裏切ったのか?」そこに話は行きつきます。
2チャンネルから引用するのもなんですが、ま、パロディーとしていえば、
「信長が生きていたら日本は巨大化して中国になってたから、未来人がタイムスリップして光秀をそそのかしたんだよ」
「おまえ・・・タイムパトロールに捕まるぞ」
・・・・・・・かもしれない。あの時、光秀変だったし(待て)
実は本能寺の変の時、信長が二十名ていどしかいない時に、15000の兵を全部本能寺に投入しております。光秀は(^^;;
ちなみに長男「信忠」も京都にいるし、堺には徳川家康もいるし、兵を分けて対処すればいいのに、全部信長(本能寺)に投入・・・
どれだけ信長が怖かったんだよ・・・(汗)
頭のいい光秀らしくない行為に、朝廷陰謀説とか、足利義昭陰謀説とか、単にノイローゼ説(待て)まで、この種の論は多岐にわたります。
信長は国内にとどまらずに海外にも進出しそうなので、それを見た朝廷が光秀に命じた、というのが真相かとも思いますが、これは自分の推論です。参考にしないでくださいませ。
まあ、今日はこんな感じでタイピングを止めたいと思います。
本能寺は、確かに歴史を変えています。というところでコーヒータイム。またです( ^^) _U~~
本日のテーマは・・・このテーマは語りつくされすぎなんだけど、これが有ったのと無かったのとでは確実に歴史が変わっている事件。
「本能寺の変」を語りたいと思います。
この事件の後に天下人になるのが、豊臣秀吉、徳川家康。
上の二人は、金ヶ崎の戦いで「しんがり」を務めるほどのオールラウンドプレイヤー。
でも、信長にとっては部下なんですね。
家康は一応同盟者ではあるんだけど、勢力的には三河周辺の地域が中心の東海部門担当という感じ。
秀吉は信長の部下なんだけど、秀吉級の部下は他にも、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、滝川一益などがいます。
ちなみに信長が部下をほめるとき、一番最初にほめるのが明智光秀。秀吉は三人目くらいなんです。
一番トップは信長で長男に信忠もいる。
えっと、そのまえに何故、秀吉と家康がオールラウンドプレイヤーなのか、というのを説明します。
「しんがり」というのは逃げる時に一番最後で待機して、勢いにのってる敵が来たら追い払って味方を逃す、という戦いです。
もし敵に大将級の首が有ったとしても見逃さなくてはならない。逃げながら戦い、味方を生きのばせることに全力を尽くす。
戦いには、例えば突撃が得意な人、城攻めが得意な人、いろいろいます。でも左記に書いたのは、全部勝っている時にこそ影響力を発揮するものです。
負けている時に突撃が得意でも意味がない、城攻めが得意でも意味がない。敵側がそういった人を差し向けてくる。
そこを守り、追い払い、できるかぎり味方を生きのばらせる。敵が襲ってきたら被害を最小限にとどめる。
防御力と相手を追い払う攻撃力と戦略的な判断が出来る人材がいる、ということになります。
その戦い、信長が負けた金ヶ崎の退き口で、しんがりを務めたのが羽柴秀吉と徳川家康。
名古屋だったかな?この戦いをトップの信長も含めて三英傑のそろい踏みとか呼んでいるそうです。
話しがそれました。元の話題、本能寺の変にもどすと、
もし、光秀が裏切らなかった場合、このメンバーが全員信長の指揮の下で天下統一するわけです。
秀吉は同格の柴田勝家とかを滅ぼしておりますが、その必要もなくなる、と。
信長自身も長篠の戦いで、鉄砲使って武田騎馬隊を撃退とか、効果的な戦略を次々とたてていきますので・・・
他にも政経一体の都市構想(岐阜城)とか、信長はどんどん新しい発想を浮かべ実現していく。
信長が作った城の有名なものに安土城とかありますが、本当は信長は大阪に建てたかったんじゃないかな?
信長が生きていたころは、大阪には石山本願寺がありまして、抗争中でしたので。
秀吉はちゃっかり自分の案として受け継いだ、と。
大阪の利便性も述べておきますと、大阪は平野が二つあって都市が作りやすく、目の前に大阪湾が有るので海上輸送された品物を大阪にすぐに輸送することが可能であり、陸路だと日本の中心にあたり、淀川から真水を確保できて、その川を通って琵琶湖にまで船で水上輸送が出来るという、たぶん信長の構想「政経合体の都市構想」には一番の適地だったかと思います。
でも石山本願寺が抵抗していたので、信長の代では果たせなかった。そこを秀吉が受け継いだ、そういうことになるかと。
うん、さらに話題がそれました。話を元に戻すと、
「明智光秀はなぜ信長を裏切ったのか?」そこに話は行きつきます。
2チャンネルから引用するのもなんですが、ま、パロディーとしていえば、
「信長が生きていたら日本は巨大化して中国になってたから、未来人がタイムスリップして光秀をそそのかしたんだよ」
「おまえ・・・タイムパトロールに捕まるぞ」
・・・・・・・かもしれない。あの時、光秀変だったし(待て)
実は本能寺の変の時、信長が二十名ていどしかいない時に、15000の兵を全部本能寺に投入しております。光秀は(^^;;
ちなみに長男「信忠」も京都にいるし、堺には徳川家康もいるし、兵を分けて対処すればいいのに、全部信長(本能寺)に投入・・・
どれだけ信長が怖かったんだよ・・・(汗)
頭のいい光秀らしくない行為に、朝廷陰謀説とか、足利義昭陰謀説とか、単にノイローゼ説(待て)まで、この種の論は多岐にわたります。
信長は国内にとどまらずに海外にも進出しそうなので、それを見た朝廷が光秀に命じた、というのが真相かとも思いますが、これは自分の推論です。参考にしないでくださいませ。
まあ、今日はこんな感じでタイピングを止めたいと思います。
本能寺は、確かに歴史を変えています。というところでコーヒータイム。またです( ^^) _U~~
Posted by white_yamada at 06:10│Comments(0)